(この新聞社ばかり取り上げて、申し訳ありませんが)毎日新聞の朝刊1面には、「余録」という看板コラムがあります(朝日新聞の「天声人語」のようなもの(;^_^A)。
「帝室は政治社外のものなり」…
https://mainichi.jp/articles/20240625/ddm/001/070/099000c
6月25日に、掲載されました。このコラムは、ありがたいことに、全文読むことができます。
「帝室は政治社外のものなり」。福沢諭吉は「帝室論」で皇室は伝統的に政治の圏外にある存在と説いた。英国流の「王は君臨すれども統治せず」に通じる。
こんな書きだしで始まりますが、昭和天皇さまは皇太子時代の訪英でジョージ5世から立憲君主制の考え方を聞き、戦後「その時以来、常に立憲君主制の君主はどうなくてはならないかを考えていた」と語っておられたそうです(私見では、この部分については私の認識はちょっと違いまして、昭和天皇さまは、戦前よりすでに立憲君主としてどうふるまるべきかは、充分意識されていたと思います)。
上皇陛下は、前記したジョージ5世伝を学ばれ、併せて(福沢諭吉の)帝室論を学ばれたことが、書かれております。ポイントは、皇室には英国流の考え方が引き継がれてきて親和性がある、ということです。
そして、天皇陛下・皇后陛下は、現在国賓として、チャールズ国王に招かれています。このコラムは、以下のような形で結ばれています。
チャールズ国王はかつて一緒に釣りを楽しんだ天皇陛下をがん公表後初の国賓に迎えた。英文化に通じ、「テムズ川の水上交通史」にも詳しい陛下への親しみの表れに思える。
それから、同日の夕刊1面のコラム「近事片々」より(朝日新聞の「素粒子」と比較して申し訳ありませんが、同じようにアフォリズム(断章)で表現したコラム)
背負い投げを食らわされた顧客の不信深く…https://mainichi.jp/articles/20240625/dde/001/070/017000c
*デジタル版により、一部をよむことが可能です。
関係あるところを、引用します。
水問題は「それぞれの国の社会や文化を理解することにもつながります」と話される天皇陛下。見識まさに。
現在、毎日新聞を始め、連日、現地の様子に関する記事が配信されていますが、こういうコラムを紙面に掲載するところが、私にはさりげないように思いました(皇室と王室、国は違えど、聖域で育んだ伝統は共有されていて、「皇位の継承」というものは親から子へという自然な流れに見えます、と。この形で存続されることが、両国にとって望ましいと)。
ご参考までに
ナビゲート:「愛子天皇への道」サイト編集長 基礎医学研究者

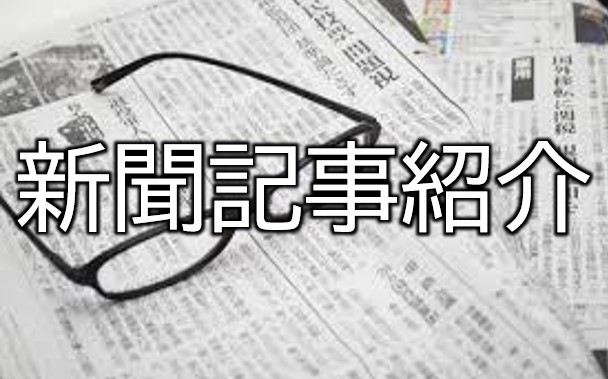
3 件のコメント
基礎医学研究者
2024年6月27日
>サトルさん
コメントありがとうございました。いや、そうなんですよね。毎日新聞の今回のコラムって、やはり「皇室の存続」のことを社としては意識している、という(読者への)アピールと自分も思いました。そうでなければ、あのような書き方はしないと思うのですよね。それから、「私見」の部分については、同意してくれる人がいてよかった。なんか、昭和天皇さまの戦前と戦後は違うみたいな言い方をする人が結構いるようですが、昭和天皇さまにとっては、「象徴」という言い方は戦後にでてきた言葉ですが、天皇としての振る舞いは、戦前も戦後も権威をになう「象徴」で変わらなかったのでは。ただし、違いがあるとすれば、それはその時の国際情勢の違いで、運命としかいいようがないですね。毎日新聞さんには、軍事・外交に関することはあまり期待しませんが、それでもこのコラムはよかったですね。
サトル
2024年6月27日
追記
ジョージ5世に……中略……会談の場を設けてもらった……です。
サトル
2024年6月27日
さすが毎日新聞!
この話は、私も……実はとても重要なこと……と考えています。
NHKで放映された「バタフライエフェクト」では(エリザベス1世の回)、皇太子時代の昭和天皇が、ジョージ5世に「昭和天皇は皇太子時代より、かねてより考えていた、立憲主義における君主のふるまいを……参考に……」と当時の映像と共に現代のナレーションで紹介されています。
基礎医さん。
ここは基礎医さんの私見で、全く問題ない……と思いますよ。
「日英同盟」の関係もあり、皇居に最も近く、国内最大敷地面積の大使館でもある英国大使館。
いやぁ、さすが「このタイミング」で出す、毎日新聞!……ですね。