- 【王墓の移動にみる、盟主権の移り変わり】~「世襲」はいつ、確立されたのか?~
最近の研究では、所謂「古墳時代」と呼ばれる時代は、3世紀中頃(西暦にして260年前後)がスタートとされています。 卑弥呼の没年ともそれ程離れていない、みたいですよ。
一般に「古墳時代中期」とされる4世紀末~5世紀にかけて、奈良盆地南東部の「やまと」の地~盆地北部の曾布地方(佐紀古墳群)、そして「大仙陵古墳」で有名な百舌鳥古墳群や、古市古墳群のある大阪平野へと、王墓の密集地も移り変わっていきます。
白石太一郎氏はこのような移り変わりを、初期ヤマト政権の政治連合内部における「盟主権が大和の勢力から河内の勢力に移動した可能性が大きい」と分析しています。
『河内のオッサンの唄』で有名な、あの河内です(※個性派俳優、川谷拓三の出世作の主題歌らしいです(;^_^A)
もっとも、白石氏はあくまで、古墳の造営システムそのものに変化が見られない事や、大和以来の政治・生産機構を河内の勢力も継承したと思われる事から、「王朝交代説」に関しては否定的ですが、『記紀』の系譜が100%正しいという前提がなければ、かなり苦しい解釈だと言わざるをえません。
前回みたような、必ずしも「血縁による世襲」ではない、政治的実力者の中から王が選ばれる「群臣推挙システム」を基盤として考えれば、それぞれに勢力基盤の異なる豪族から推挙された王が、全員「一族」だったという固定観念を持つ方が、こうした王墓の立地移動に照らし合わせて考えても、むしろ不自然なのかも知れません。
義江氏によれば、「世襲王権」が確立されたのは、第26代継体天皇の第三皇子である欽明天皇の子孫以降であり、それ以前は「王」は古くからいたが、社会的存在としての「王族」がいたというわけではないようです。
(中の中編のオマケ)につづく
文責 北海道 突撃一番

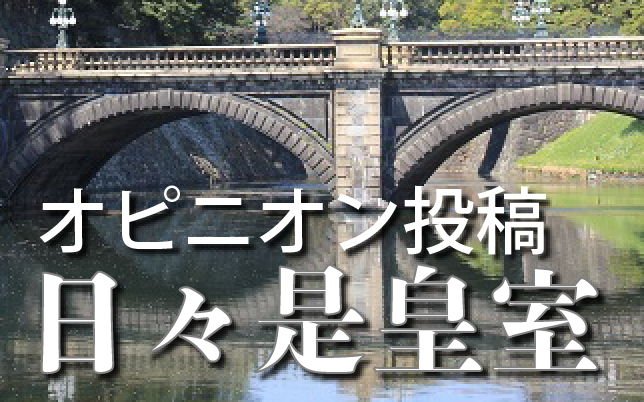
4 件のコメント
突撃一番
2023年3月27日
最終回まで出典出さないのは流石にマズイと思いましたので、今回の投稿での主な参考文献を明示しておきます。
白石太一郎『古墳とヤマト政権』~古代国家はいかに形成されたか~
平成11年4月20日 第二章~第三章
天皇陵を含む大規模古墳の移り変わりが、詳しく理解出来ますよ。
基礎医学研究者
2023年3月26日
(編集者からの割り込みコメント)今回も、勉強させていただきました。といいつつ…『河内のオッサンの唄』で来るとは思わなかったので、ちょっと意表をつかれました~(^_^)。これは、自分が関西人ではないからなのでしょうか?川谷拓三といえば、自分的には映画「ビルマの竪琴」や「226」でしたかね。閑話休題。
なるほど、たしかに義江氏の研究の形で推し進めると、万葉一統が成り立たなくなる可能性も高いですね(これは、皇統譜を軽視している訳ではないのですが、皇統譜と研究は”分ける”という態度が、誠実な気がしてきました)。なので、結局のところ”何が”皇室で継承されてきたのか(自分は、エートスだと思いますが)を私たちは意識すれば、それで充分!ということになりそうな気がしております。次回も、楽しみにしております。
突撃一番
2023年3月25日
京都のSさん、コメントありがとうございます!
武烈天皇の事例然り、なかなか古代から一貫して「シラス」存在というわけにはいかないみたいですね。
権威と権力の分離も、2000年の積み重ねが必要なようです。
京都のS
2023年3月25日
「勢力基盤の異なる豪族から推挙された王が、全員『一族』だったという固定観念を持つ方が、こうした王墓の立地移動に照らし合わせて考えても、むしろ不自然」ですか。うーむ。万葉一統説すら怪しくなるわけですか~。
ウシハク存在の豪族たちが推挙して最終的に立った王だからこそ、公平無私なシラス存在(存在意義の面でも後世の天皇につながる)になれるのかもしれませんね。