【イントロダクション】

最初に断っておきますけど、今回のブログでナザレンコ・アンドリー氏に「論破祭り」を仕掛ける意志はありませんから。
むしろ「考えるキッカケ」を与えてくれたお礼に、反論ならキッチリ「X」上でやらせていただきましたんで(笑)

勿論、男尊女卑云々のセリフは、挑発するつもりで言ったんですけどね。
現在のウクライナ領である、ドニエプル川周辺に端を発するコサックはどうやら、軍事的共同体だったらしいんですけど、今のウクライナという国家がホントに平素から男尊女卑の国かどうか、軽く調べただけでは不明だったので、結論を出すのは控えさせていただきます。
しかし、先日の「ゴー宣DOJO」(第2日目)において、よしりん先生が「近隣諸国に逃げたウクライナ国民のビザ発給が停止されて、戦う為に祖国に帰還させている」と指摘されたように、戦時下である現在のウクライナにとって「男手需要」が高まっている事だけは確かです。
勿論今のウクライナは、将来の日本の姿です。
中露が日本を侵略してくれば、日本男児は好むと好まざるとに関わらず、戦わざるを得ないでしょう。
※ だからせめて、平時のうちに「戦闘訓練」くらいはやっとけ!! というのが、私がX上で「徴兵制実現」を主張する理由の一つでもあるんですけども。
まあそれはともかく、「戦時下における一時的な男手需要」は仕方ないとして、
それがひいては、戦争勝利によって平和を取り戻した後の国家においても「男性優位社会」として固定化され、女性の地位低下を招きかねない事は、戦国時代の終焉と共に始まり、260年以上も続いた近世の武家社会を見ても、危惧しておく事は決して考え過ぎではないと思います。
この時代の2方の女帝は、古代社会と違って明らかに「中継ぎ」でしたもんね。
今回は、以下の4回シリーズ。
1「男女双系」から、「男性優位」へ
2 国防の為の「戸籍」
3「男手需要」と「男社会」は違う??
4 なぜ、「女系天皇」なのか?
冊封体制への編入に端を発し、特に平安時代以降の日本に顕著に見られる「女性の地位の低さ」と軍事との関係がどのようなものだったのかを、今回は軽くではありますが、考察してみたいと思います。
今回あえて、「直系継承」でも「男女双系」でもなく、「女系天皇」とサブタイトルで表記したのは何故なのか・・・?
是非最後まで読んでね!!
文責 北海道 突撃一番

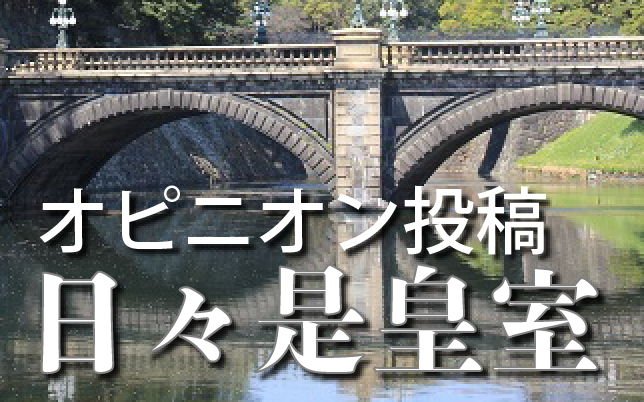
4 件のコメント
突撃一番
2024年6月14日
基礎医さんも、いつも秀逸な編集ありがとうございます!
後半は少々小難しい話になりますが、よろしくです!
基礎医学研究者
2024年6月13日
(編集者からの割り込みコメント)寄稿、ありがとうございました。自分、編集していて、3の「男手需要と男社会は違う?」というところが、けっこうポイントな気がしています。次回を、楽しみにしております。
突撃一番
2024年6月13日
掲載&コメントありがとうございます!
京都のSさんご指摘の、律令導入と同時に儒教の影響も受けていたというのは、今まで意識した事無かったです。
確かに、律令の表彰規定も儒教的規範によるものらしいですね。
今津勝紀『戸籍が語る古代の家族』によれば、有力豪族の中にはこの頃から既に、夫の戸籍に妻が編入され、男女が同居する事も普通に行われていた事が指摘されています(p151~)。
『光る君へ』でまひろの父が、事あるごとに「お前が男に生まれてくればよかったのに・・・」とぼやいてる事にも顕著なように、平安中期にもなると、男性優位は下級の貴族辺りには浸透していたのかも知れませんね。
京都のS(サタンのSでも飼い慣らすし)
2024年6月13日
硬質な論考が始まりましたね。
「戦争勝利によって平和を取り戻した後の国家においても『男性優位社会』として固定化され、女性の地位低下を招きかねない事は、戦国時代の終焉と共に始まり、260年以上も続いた近世の武家社会を見ても、危惧しておく事は決して考え過ぎではない」
この後半についてですが、戦国期~江戸期には特殊事情があります。直ぐに刀を抜く戦国武士を治世の官僚に変えるために朱子学を官学とした史実も、260年間の安定的な男尊女卑体制の理由かと思われます。また「平安時代以降」は、大河「光る君へ」でも明らかなように女性が生き辛い世ですが、律令と共に受け入れた儒教の副作用が影響していると思われます。庶民も一般貴族も通い婚&婿入り婚なのに、皇室の後宮だけは準・嫁入り婚になっていましたから。
従って男性性のプレゼンスが高まった時代(対外戦争時代)の後には男系主義が根を下ろさないように注視しておく必要があると思われますね。
次回も楽しみです。