【大嘗祭③ ~“ウシハク”存在から、公民へ~】
前回ブログに引き続き、高森明勅氏の『天皇と国民をつなぐ大嘗祭』をテキストに、もう少し天皇と庶民との関係性を見ていきましょう。
高森氏によれば、大嘗祭が現在のような形になったのは、持統天皇の時代だそうです。在地の民による天皇即位儀礼への奉仕を実現するには、諸豪族による私的・個別的支配を脱し、国家による公的な統治の下に生きる「公民」である必要があります。
・・・だって、考えてもごらんなさいな。
顔すら見た事ない人から、ある日突然文書だけで通達が来て、「今日から私が、アナタ方のトップリーダーです。ひいては就任式やりますんで、アナタ方が大事に育てたお米を、がんばって東京まで運んできてね❤」
とか言われて、誰が納得しますか??
645年(と、我々オッサン世代は中学校で習ったんだが)の「大化の改新」によって、所謂(いわゆる)「公地公民制」が確立され、民衆は天皇の統治下にあるとされた、というのは一般的な解釈です。
とはいうものの、大化二年(646年)正月に、「臣・連・伴造・国造・村首の所有(たもて)る部曲の民・処処の田荘(たどころ)をやめよ」
つまり、中央・地方の豪族らの、土地と人民に対する個別的支配を全て停止せよ、という内容の詔が発せられたとはいえ、それまで強固な伝統を築いてきた豪族層と地方民の領有関係は、なかなか簡単には“卒業”出来るものではありません。
まあ、盃を交わした親子の契りは、そう簡単に“お白紙”には出来やせんって事でござんしょう。
天智天皇9年(670年)の庚午年籍の成立を経て、675年の天武天皇の詔によってようやく「公民」という身分が成立したと、高森氏は分析しています。
その事を裏付けるかのように、『日本書紀』天武天皇二年12月の「大嘗(おおにえ)」の記事に、播磨・丹波の地方民による奉仕が確認されています。
ただし、天武天皇治世では、天皇が即位された年ばかりでなく、毎年行われる新嘗祭までが大嘗祭と同じ方式で行われており、従ってまだ「天皇即位儀礼としての大嘗祭」が成立したとは言えません。
『飛鳥浄御原令』の規定に基づいて初めて行われたものとして、持統天皇の大嘗祭を“第一回”であると高森氏は分析しています。
【“公地公民”に関連する蛇足論考】
ところで、話は急に現代へと移りますが、現在の日本人は本当に、「公民」と呼べる存在なのでしょうか?
前回「ゴー宣DOJO」のテーマとも若干被りますが、結局、資本主義のゲームルールを熟知して、それに則って成功を収めた「銭ゲバ経営者」が、例えば軍人とか、子を産む女性よりも地位が高い、という状態を、大企業優遇政策によって固定化させてるのが、今の自民党政権なのではないでしょうか?
だからこそ、産休・育休を取る女性よりも、「労働力」としてアゴで使える女性の方が、賞賛されてしまう。
だからこそ、厚労省ですらタテマエでは「個人の判断」と通達しているにもかかわらず、実際には職場の上司からの圧力とかクビを恐れて、毒ワクチンを打たざるを得ない国民が、後を絶たなかった。
「在地豪族≒大企業の経営者」が、国民を“ウシハク”、つまり私的・個人的に占有する国家、というまるで「大化の改新」以前の日本(倭国)に、退化してしまったように思えてなりません。
今一度「公民」、つまり全て国民は天皇の「おおみたから」であるという精神を、思い出させる必要がありそうです。
そうすれば、厚労省の通達に従う気すらない会社の社長から「ワクチン打たなきゃクビだ!」と脅迫されても。
「たかが権力が決めた銭ゲバルールでちょこっと儲けただけの分際で、権力の通達無視してんじゃねーよこのバカ社長!!」
と、明らかに職権の範疇を超えた理不尽な命令に対しては、社員がちゃんと逆らえる社会を実現できるかも知れません。
我が主(あるじ)はただ天皇陛下お一人のみであって、会社の社長ではない!!
文責 北海道 突撃一番
参考文献
高森明勅『天皇と国民をつなぐ大嘗祭』
展転社 令和元年5月25日

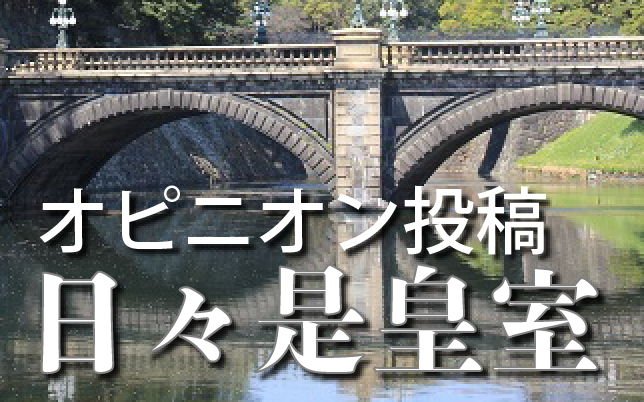
3 件のコメント
突撃一番
2024年7月6日
コメントありがとうございます!
高森先生も著書で述べておられるように、「公民」となる道は、豪族による個別的支配の否定とまさに表裏一体です。 それまで人民を支配していた豪族ですら、「天皇への帰一」を深める事で、国家組織の「官人」として吸収されていきましたから。
次々回以降のテーマとも繋がりますが、公の問題に関心すら持たない銭ゲバ経営者が社員の基本的人権をないがしろにするのは、「国民主権」の名のもとに、天皇をないがしろにするような国民に育ってしまった事も一因じゃないでしょうか?
だから「公民」という感覚すら育ってないのでは?
「社長命令に従うのがイヤなら、会社やめて自分で独立起業すりゃいいじゃねーか!」という批判も聞こえてきそうですが、それはそれで、「資本主義社会のルールで稼げる者でなければ、命令通りにワクチン打たされて、黙って企業に殺されるしかない」という事になるので、どっちみち“銭ゲバルール”の範疇を超えた事にはなりません。
でも企業の経営者を全部、古代の豪族みたいに「官人」として国家組織に組み込んでしまったら・・・?
それはそれで、共産主義社会になっちゃいますね。
やっぱり「国民主権」をやめてしまうのが、一番妥当ではないでしょうか?
SSKA
2024年7月6日
公地公民は後々荘園や武士の支配等で崩壊するのを見ても国家指導層寄りの考え方で民衆の土地所有の実状と合わなかったのではないかと前回書きましたが、一方でこの時代に整備され在地の民衆に配慮した祭祀の在り方が少しずつ変化しながら現代まで継続しているのを考えると、天皇が国家を代表し土地や民を絶対君主的に管理する考えの方が率先して排除され、民との精神的繋がりの方が異なる時代でも残っていると理解出来ます。
男系主義も明治の富国強兵の国家政策を基に過去の継承事情を無視した条項を引き継いだだけで、現在の政治家も男尊女卑が心地良い以外の理由は無く、当事者である皇室から敬遠される邪な考えでもあるので自ずと廃される結末は決まっていると見て構わないでしょう。
京都のS
2024年7月6日
圧倒的に蛇足論考の方が面白いですね(笑)。ちなみに銭ゲバ経営者=内外のグローバリストである点も注目されるべきです。つまり日本国民をウシハク存在は外資(米欧中)も多いという視点も重要です。
「資本主義のゲームルールを熟知して、それに則って成功を収めた『銭ゲバ経営者』が、例えば軍人とか、子を産む女性よりも地位が高い、という状態」は本当に大問題です。子を産むことには命のリスクが伴いますから、男なら軍人レベルでないと等価交換できません(同等と思われたければ徴兵制が必要)。にも拘らず、命のリスクが絶無なのに動かすカネの多寡で地位の高さが決まると思われている現状は異常中の異常です。この異常を解消する方策が「一君万民」を認識することだという論陣には感動させられます。次回も楽しみです。