【大嘗祭② ~地方郡司による奉仕~】
古代社会の「国司」と「郡司」って、歴史の授業とかで習った事ありますか?
冒頭からいきなりマジメトークはあんまり好きじゃないんだけど、前回ブログで十分ボケ倒したので、今回はネコを被って、突撃一番は極めてマジメな人格であるかの如く偽装させていただきます。
ざっくり定義すると、
国司=中央(都)から派遣された役人
郡司=地方豪族出身者の長
このように分けられます。
郡司はまさに、在地の共同体秩序を統括する者でもあり、律令国家の統治機能を地方末端まで行き届かせるという、極めて重要なポジションだったと言えるでしょう。
『日本書紀』『続日本紀』においては、大嘗祭のパイオニアと呼んでも過言ではない持統天皇にはじまり、聖武天皇までの大嘗祭における在地奉仕者に、国司の名は全く記載されていないそうです。
また、大嘗祭における在地奉仕者の中で最も重要な役割のひとつに、「造酒童女」(さかつこ)という女の子がいます。
斎田から稲を収穫する際など神事における重要な場面で、まず最初に手を下したり、供え物を都まで運ぶ際に輿に乗って上京するなど、奉仕者の中でも造酒童女は、特に、神聖な存在とされていた事がわかります。
造酒童女には、斎郡に選ばれた郡司の未婚の娘が、占いによって選ばれました。
ところで、造酒童女の萌えキャラ化イラストとか、だれか描いてくれないかね?? アーニャみたいな感じで。
中央から派遣された国司が音頭を取るのではなく、まさに「土着の共同体をあげての奉仕」によって大嘗祭が、ひいては天皇即位の正当性そのものが成り立っていた事がよくわかります。
・・・という、見事な研究成果を書籍化してくださったのは、なんとこの方です!!⇩

われらが師範・高森明勅先生で~す!
読もう!読むしかない!!
文責 北海道 突撃一番
参考文献
高森明勅『天皇と国民をつなぐ大嘗祭』
展転社 令和元年5月25日

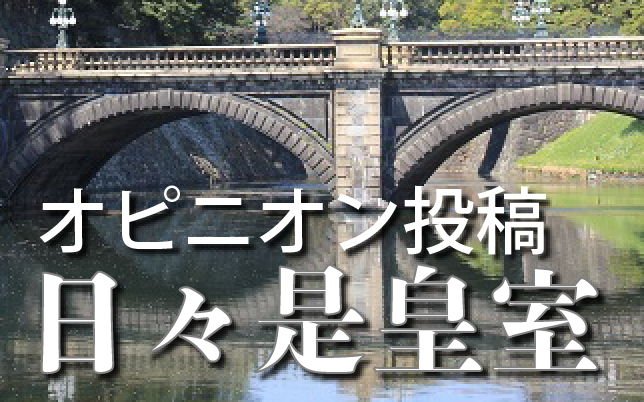
3 件のコメント
突撃一番
2024年7月5日
皆さん、コメントありがとうございます!
今回紹介した書籍において、高森先生は、毎年恒例で行われる新嘗祭と、皇位継承にともなう儀礼としての大嘗祭を、明確に区別する決定的な要素こそが「在地の民の奉仕」だと述べています。
今回、「天皇とポピュリズム」の関係を私が論ずるにあたって、大嘗祭の歴史に触れる事を避けては通れんな、と考えたのも、その為です。
国民の一時的な社会への不満をうまいこと吸い上げて、既存の権力・権威を攻撃する道具に使う程度の“カリスマリーダー”なら、歴史上幾度となく現れましたよ。
「自民党をぶっ壊す!」と煽り散らした小泉純一郎とかも、まさにその類かな?
天皇と国民との関係性は、そんな浅はかなもんじゃないよ。
今のところ言えるのは、それぐらいかなぁ。
SSKA
2024年7月5日
律令制と共に日本の事情に配慮しつつ古代に制度化された公地公民は時代を経る毎に崩れ形骸化してしまいますが、日本人元来の土地への執着や実状と合わなかった為なのか気になります。
シナに高望みしただけの男系思想も同じ道を辿る以外考えられませんが、現存する確固たるものとして天皇の祭祀を通じ土地と収穫物を介して公と民衆が繋がる精神が修正されながら生き続けている事が特に重要に感じます。
かつてなら民衆、現在は国民の意識を捉えなければ過去に天皇が続いた独自性には触れられずに自然な敬愛が生まれる事も無いと改めて感じました。
京都のS
2024年7月5日
真面目に開始しても笑える要素をふんだんにブッ込んでくるのが突撃様でしたわ(笑)。
「造酒童女の萌えキャラ化イラストとか、だれか描いてくれないかね??…アーニャみたいな感じで」は、フェミが「性的搾取批判」の文脈で吠えるでしょうし、それを可愛く描けば描くほど「ルッキズム批判」でも文句を付けるでしょうね。全くウザったい時代になりました。
ラストの告知は「そうきたか」って感じです(笑)。