読売新聞からの記事です。
日英 かけがえのない友人…ジュリア・ロングボトム駐日英大使寄稿
https://www.yomiuri.co.jp/world/20240712-OYT1T50008/
この記事は、7月12日朝刊(国際面)に掲載されました(今回は読売新聞の記事ですが、デジタル版で全文が読めます)。これはタイトルが示すように、ロングボトム駐日英大使から寄稿された文章で、こういう政財界に影響力のある立場からの寄稿が寄せられるのは、読売新聞の強みだと思います(読売新聞、さすがです!)。
天皇、皇后両陛下が、英国での国賓訪問を終えられ約2週間がたった。今回のご訪英は、日英関係がかつてなく強固に発展しているタイミングにおいて実現された。両国の緊密な信頼関係と未来志向のパートナーシップが象徴された、歴史的な国賓訪問に携われたことを大変光栄に思う。
書き出しを引用しましたが、これは外国の大使としては、最大の賛辞だと思います。
このあと、訪英における天皇陛下やチャールズ国王のご様子が記述されているのですが、私見では皇室に関心のある方には是非一読いただきたい、見事な要約かと思います。その中で、私が注目した箇所を箇条書きにします。
・(天皇陛下のお言葉にあるように)英国には古いものを大事にする一方で新しいものを生み出す、伝統と革新の調和を大事にする精神がある(私見では、これは日本においても本来そうである、という意味を内包していると思います)。
・日英関係の交流の礎(いしづえ)にとなるものは、長年にわたる人と人との交流とつながりに裏打ちされた絆(きずな)だ。次の世代を両国間で築かれた絆が、次の世代を担う若者や子供たちに引き継がれ、更に進化していくことを期待する。
そして最後に、
自然や科学、文化・芸術、教育に至るまで、日英間の重層的な連携・交流は加速しており、今まさに、我々は日英関係の新時代を迎えている。天皇陛下はお言葉の中で、両国が(現在だけでなく未来に向けても)「かけがえのない友人」であると強調されたことを紹介し、大使自身もそれを確信していることを結論、としております。
私、この寄稿は、日本の皇室・英国の王室、双方に寄り添った、非常にフェアな論考と思いました。そして、皇室・王室の存続を確信しておりますね。(それは、私たちと同じかと。外圧に頼るわけではありませんが、どうでしょうかね?)
ご参考までに
ナビゲート:「愛子天皇への道」サイト編集長 基礎医学研究者

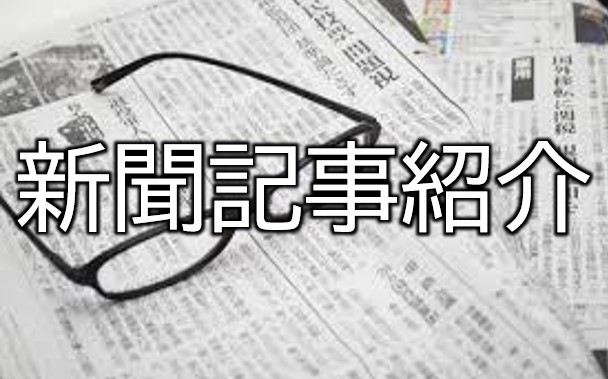
8 件のコメント
昭和43号
2024年7月15日
コメントが遅くなりすいません。
オーディエンスいいですね。
前によしりん先生と木蘭さんが話しているのを聞いて初めて知りました。
日本にもあれば、権力の私物化を抑制できるかもしれないと考えたこともあります。
安倍元首相のような朝敵だと、陛下の御意見でも無視しかねないですが。
皇室と同じく長い歴史を有するイギリス王室には見習うことが多いと思います。
パワーホール
2024年7月15日
基礎医学研究者さん
詳しいお話と御忠告ありがとうございます。
基礎医学研究者
2024年7月14日
>パワーホールさん
これは、編集者というよりも、科学者の立場でちょっと書かせてもらいます。イギリスが、かつて「優生保護法」を作った歴史的経緯があることは否定しません。ここには、科学者だけでなくあらゆる階層の人が関与していたでしょう(むしろ、G.Kチェスタトンのような人の方が、例外的存在と、自分は思います。)。
しかし、ダーウィンが積極的に優生学に関与した!?という、証拠はどこにあるのでしょうか?どちらかというと、優生学を推し進めたのは、ダーウィンの従妹で遺伝統計学者のフランシス・ゴルトン(指紋の遺伝的特性を測定したことで有名)や、さらにそれを広めていった知識人なのでは?
自分にいえるのは、ダーウィンの進化論(自然淘汰理論)は、「集団の中で環境に適応したものが次世代に形質を伝えて種を形成する、すなわち進化する」という理論だったため(ちなみに、ダーウィンは当時、遺伝のメカニズムを知らなかった)、これを弱肉強食の生存闘争と置き換えられ、優生学に利用された(ゴルトンのような人に)というのが、実際のところでは。ダーウィン自体は、進化理論を確立した「種の起源」においては、むしろ人間を論じることは意識的に避けていた、と言われています(たぶん、自然科学の範疇を越える、と判断したからでしょう)。
で、これだけは言っておきたいのですが、ダーウィンはデータを重視した実証的な科学者で、ものの言い方はかなり慎重でした。なので、後々まで同業の科学者にも尊敬されたような存在。一方、竹内久美子は、どうでしょうか?「伝統のY」とか狂信的なことばかり言っているから「研究家」としか名乗れない存在で、とてもではないが、ダーウィンとは同列には扱えないでしょう。なので、自分はその意見を支持しません。
で、今後のこともあるので書いておきますが、自称保守を批判したいがために、根拠の薄い話を出してきてまで自分の意見に引き付けるのは、止めてほしい。かりにもゴー宣DOJOに参加し、その思想を理解しているというのならば、もう少しバランスのよいコメントをお願いします(なお、これは「愛子さま」サイトの共通見解ではなく、私、基礎医、個人の意見であることを、付記します)。いかがでしょうかね?
基礎医学研究者
2024年7月14日
(編集者からの割り込みコメント)
みなさん、コメントありがとうございました。
イギリスについては、自分もみなさんいわれるように、基本思考が日本により親和性があると思います(そこは、アメリカと比較すると、特にそう思います)。政治レベルでは、確かに昭和43号さんいわれるようにアメリカに追随するもろさを露呈することがありますが、王室は政治から切り離された”権威”を担っているので、おそらくそこは政治家とは異なるのでしょうね。自分は、皇室や王室には世俗を越えた部分はやはり必要、と思います(ただ、未来的にはイギリスのオーディエンスは、取り入れてほしい部分ですよね)。
最後に、SSKAさんの言われる最初の部分、「八幡の様ないい加減な人間と違って・・・」は説得力を感じました。八幡は元官僚かもしれないけど、発言の重みが大使とは全然ちがう!その通りかと、思う次第です。
パワーホール
2024年7月14日
京都のSさん
EバークやGKチェスタトンを輩出した国とありますが、日本の自称保守はバークやチェスタトンよりかダーウィンの方が好きみたいですね。だからY染色体やら血統やら言い出したり優生保護法作って「一君万民」を否定したりするのだと思います。それに、ダーウィンは竹内久美子とたいして変わらない人物だと考えています。ちなみに、チェスタトンはダーウィンや優生学を批判しています。自称保守派には、バークとチェスタトンの著作をしっかり読んでほしいです。
昭和43号さん
水を差すようですけど、アメリカもフランスもイギリスも相いれない部分があるので警戒しつつ付き合っていくのが妥当だと思います。
昭和43号
2024年7月14日
イギリスは王政を望む民衆が多かったこともあってか、人民主権や人権主義といった近代政治思想の発祥地でありながら、革命の破壊力はフランスほどではなく、自由主義や民主主義への移行は漸進的でした。
伝統と革新の調和、少しずつ変わり続ける保守の理想ですね。
日本と同じ立憲君主制で、双系継承の良き先例でもあり、フランスより見習うことが多いかもしれません。
ただイギリスも日本と同様に、アメリカに従属する傾向があるので、是々非々で参考にすればいいと思います。
SSKA
2024年7月14日
八幡の様ないい加減な人間と違って責任ある立場の方の意見はやはりこうなりますね。
皇太子時代のご夫妻の祭祀の問題で高森先生が触れていたのと似ていると思いましたが、極論を言えば天皇陛下さえ万全な状態でチャールズ国王との対面が行われれば両国間の目的は果たされた中で、ご体調が優れない皇后様が公の場に出席された事でお役目への責任感と常に助け合う両陛下の絆の深さが感じられ、各所でご配慮のあった英国の歓迎ぶりからは皇室を大切にする心が伝わり、伝統を重んじる東西の国同士で互いを思いやりながら未来の発展を目指す姿勢が伝わった素晴らしい内容だったと素人目には写りましたし、評論の場でも戦争の過去を払拭するものだったと賛辞が占めています。
君主家同士の感情のやり取りから双方の国民も自らを顧みたり学ばされた部分も多かったはずで、人の心を介さない君主制は存在し得ない実情と共にご夫妻の後を継がれるのに相応しいのは誰かも余程現実を見たくない者以外、自ずと気付かされるご訪問だったのではないでしょうか。
京都のS
2024年7月14日
「英国には古いものを大事にする一方で新しいものを生み出す、伝統と革新の調和を大事にする精神がある」の部分は保守の真髄ですね。さすがEバークやGKチェスタトンを輩出した国です。これは、これまで皇族方が述べてこられた伝統観とも一致します。変えてはいけない核心部分(伝統)と時代に合わせて変えるべき枝葉末節(因習と化した儀礼定な事物)との差を最も強く認識しておられる当事者が皇族方だからです。皇室も英王室も同じ伝統保守の立場であるなら、「未来に向けてもかけがえのない友人」となれるはずです。