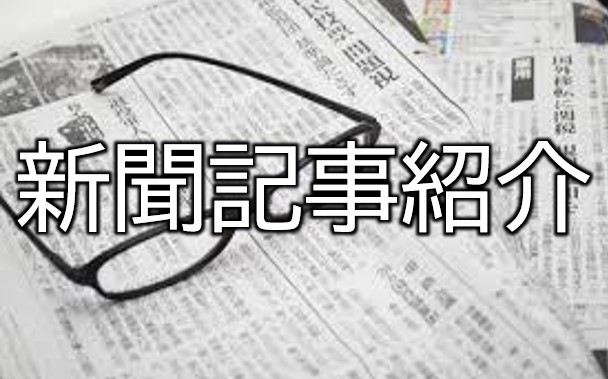毎日新聞の記事です。
両陛下が追悼式に 戦後世代にも受け継がれる平和への思いhttps://mainichi.jp/articles/20240814/k00/00m/040/187000c
*デジタル版で、一部を読むことが可能です。
本日(2024年8月16日(金))朝刊の5面(総合面)に、掲載された記事です(山田奈緒記者による)。紙面では、”継承する慰霊の思い 追悼行事 幅広く参加”というタイトルで掲載されていますが、私見では、こちらの方が皇室の方々の感覚が、うまく表現されているように思えます。
前半は、昭和天皇さまの最後の追悼式の様子が書かれています(ここは、自分、よく知らなかったので、勉強になりました)。
続いて、後半の”おことば踏襲”では、追悼式の歴史を追っています。ですので、最初は昭和天皇さまから始まりますが、この記事には現在の両陛下、そして小さいときの愛子さまのお写真が掲載されているのは面白く、山田記者が現在の視点からこの話題を振りかえっている、と理解しました。
紙面でしか読めない箇所について、一部引用します。
政府主催の初めての追悼式は、サンフランシスコ講和条約発効で主権を回復した4日後の52年5月2日、新宿御苑(東京都)で開かれた。「戦争に死し、職域に殉じ、また非命にたおれたものは、挙げて数うべくもない。衷心その人々を悼(いた)み、その遺族を想(おも)うて、常に憂心(ゆうしん)やくが如きものがある」。昭和天皇はこう述べた。
時代を感じさせる難解な表現ですが、”慰霊”ということが、端的に表現されていると思います。
また一番最初が新宿御苑、というのは意外だったのですが(東京都で育ったものとしては、普通に都民に開放された憩(いこ)いの場、遠足場所のイメージ強し)、その後、不定期に開催される形で、日比谷公会堂(63年)、靖国神社(64年)と場所を変え、日本武道館が完成した翌年の1965年から今の形が定着した、というのは、もっと意外です。といいますのは、この段階では、靖国神社は慰霊の地として、適当と認識されていたことになるからであります(私個人としてはこのことに何の違和感もありませんが、現在は完全に”政治問題”になっております。例えば、皇室スケッチの隣に、「木原防衛相 靖国参拝、終戦の日 中韓が抗議」の見出しの記事が掲載されています)。
節目節目で表現を変えながら、平和への思いを述べてきた。戦争への記憶が社会から薄れていく中で迎えた戦後70年の2015年には「さきの大戦に対する深い反省」との表現を初めて使った。
この部分は、山田記者も書かれているように、現在の天皇陛下にも踏襲されています。ただ、これについては、天皇は権威を体現する存在なので、ここに、日本への政治・歴史判断が入っているわけではない、と理解すれば、歴代の天皇から踏襲された「平和への思い」に変化があるわけではない?と思いますが、いかがでしょうか?
最後のセンテンス、”沖縄豆記者と交流”についてです。
沖縄豆記者とは、沖縄の小中学生が本土で記者体験をするものです。そのときの交流を通じて、上皇さまは皇太子時代に激戦地であった沖縄への理解を深めていったそうです。以下、一部を引用します。
平成のころは、陛下が当時の住まいだった赤坂御用地の東宮御所で交流を重ねた。皇后雅子さまや長女愛子さまが歓談の輪に加わったり、ご一家が豆記者と庭でバレーボールを楽しんだりもした。
結びは、このようにまとめられています。
令和になると秋篠宮ご夫妻が交流を担い、19年には長男の悠仁さまも参加した。今年は秋篠宮ご夫妻が2日、赤坂御用地にある赤坂東邸で沖縄豆記者の小中学生30人と懇談。宮内庁によると、沖縄の自然や料理が話題にのぼったという。
この記事で、なるほど!と思ったのは、沖縄豆記者との交流が、上皇陛下からはじまり、天皇家、秋篠宮家とずっと続いているということです。ここに、天皇家や秋篠宮家の区別などはなく、その時代・時代で、皇室としての役割を担っていき、国民との交流を深めたと思いますが、いかがでございましょうか?
ナビゲート:「愛子天皇への道」サイト編集長 基礎医学研究者
毎日新聞に意見を送りましょう!
お問い合わせ・ご意見など|毎日新聞社 (mainichi.co.jp)