毎日新聞からの記事です。
政治に関与しようとしつづけた 昭和天皇にとっての「象徴天皇」https://mainichi.jp/premier/politics/articles/20240807/pol/00m/010/007000c
*デジタル版で、一部をよむことが可能です。
実は、この記事、先に毎日新聞の「政治プレミア」に掲載されたようですが、「皇室」の話題については、もはや観測気球というよりも、紙面掲載前のプレ掲載のイメージが強いです。
さて、本記事は8月30日朝刊の4面に掲載されました。須藤孝記者による、昭和天皇 探った政治関与 動き抑制 納得促した側近と言うタイトルで、志学館大学教授の茶谷誠一氏へのインタビュー記事であります。
冒頭を引用します。
象徴天皇制は日本国憲法とともに突然生まれたわけではありません。特に天皇の政治関与をめぐっては、試行錯誤がありました。
ここは、須藤記者の記述ですが、もしこれが「天皇陛下は歴史・伝統的に権威を担い、象徴天皇制が日本国憲法とともに、突如生まれたわけではない」という文脈ならば、わかります。ただ私見では、どうもそれとは、異なるようです。以下、見ていきます。
前半の「象徴」議論できず(この部分は、デジタル版で閲覧可能)で、茶谷氏は、日本国憲法の「象徴」ということに関する意見を述べます。で、私、この記事で下記の言及が目を惹きましたので、以下引用します。
――昭和天皇は(「象徴」というお立場に)どう対応しようとしたのでしょうか。
◆新憲法下での自分の立場は、ある程度は理解していたと思います。しかし、一定の政治関与はできると考えていたのではないでしょうか。前提になっているのは昭和天皇がよく知っていた、英国の立憲君主制です。
1973年の増原事件(※1)の直後に、当時の入江相政侍従長に「英国首相は毎週1回、クイーンに拝謁する」と言っています。閣僚の天皇に対する国政報告(内奏)を君主の政治的権限として認識していたことがわかります。
※1 73年に増原恵吉防衛庁長官(当時)が、昭和天皇に国政報告(内奏)した後に「近隣諸国に比べ自衛力がそんなに大きいとは思えない」などの昭和天皇の発言を明らかにしたことが問題になり、辞任した。
ここは、私見では貴重な情報と思いました。「愛子さまトーーク(第164回)」でまーさんが、小林よしのり先生の「昭和天皇論」を紹介されていましたが、あの作品を読んでいるならば、昭和天皇さまの立憲君主としてのおふるまいは理解できるので、この部分に不自然な点はなく、素直に受け取れると思うのですが、いかがでしょうか?
こう書きますのは、後半の憲法違反といさめにおいて、昭和天皇のこのようなお振舞いに批判的なトーンの意見が続くからです。ここでは、初代宮内庁長官の田島道治(たじまみちじ)の昭和天皇拝謁記(※2)も引いております。
※2 先述の田島道治(1885~1968年)が49年から5年近い昭和天皇との対話を記録した書類(改変・引用 by基礎医)。
ただ、最後の部分は、茶谷氏の意図はどうあれ、象徴天皇制というのものを当事者の昭和天皇がどう考えているのかを示唆する内容を含んでいると思われますので、引用します。
――昭和天皇が(田島らのいさめに)納得したわけではありません。
◆政治的な関与をしようとする昭和天皇の動きはその後も続きます。代表的なのは増原事件です。「天皇の政治利用」と批判されましたが、本当の問題は、天皇が閣僚に政治的発言をしたことです。この時、昭和天皇は当時の宮内庁長官である宇佐美毅(うさみたけし)に「はりぼてにでもならなければ」と不満を漏らします。GHQが象徴天皇の機能として求めたのは「はりぼて」、つまりお飾りなのですが、昭和天皇は後年になっても納得していません。政治への関与を探り続けることは昭和天皇のなかでは終生変わらなかったのではないでしょうか。」
本当は、記事全体に対していろいろ思うところがあるのですが、今回その解釈はいたしません。ただ、少なくとも昭和天皇さまが、「オーディエンス」に思いをはせるていたことは、国民として非常に勇気づけられました。
いかがでございましょうか?
ナビゲート:「愛子天皇への道」サイト編集長 基礎医学研究者
毎日新聞に意見サイト
お問い合わせ・ご意見など|毎日新聞社 (mainichi.co.jp)

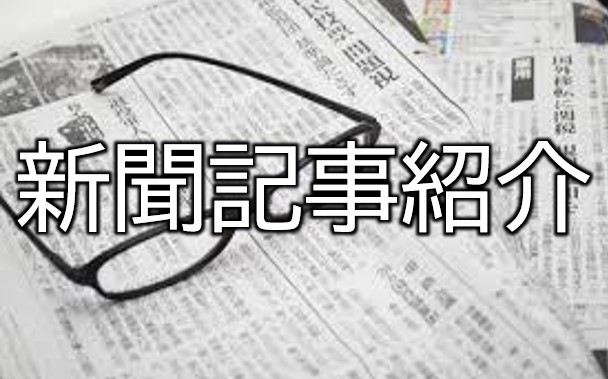
7 件のコメント
基礎医学研究者
2024年9月5日
>寝太郎さん
コメントありがとうございました。その通りかと、思います。毎日新聞を擁護するわけではないのですが、どうもたまにちょっと自分からみると”あれっ”という解釈をする方がでてくるので、やはり是々非々の姿勢は大切かと。しかし、この記事がもたらしてくれた情報が、今回は大きかったのではないかと。
寝太郎
2024年9月4日
興味深い記事のご紹介ありがとうございます。
オーディエンスはよしりん先生も指摘したように特に皇位継承については陛下や秋篠宮様の意見を聞くべきで、国民も国会議員もこの事をほとんど考えていない事に呆れてしまいます。
この記事を鵜呑みにするとオーディエンスなんてダメだとなりますが、イギリスではキチンと運用されていることなどが知られるようになるべきだと思います。
サトル
2024年9月2日
>基礎医さん
概ね同感です(ここでの″概ね″とは、直接対話する中で深まる部分があるので……の意です)。
わたくしも敢えて(笑)、言葉足らず、誤解?を恐れずコメントすれば、日本人はほぼ全員が良きにつけ悪しきにつけ、戦後民主主義の影響下にドップリ置かれています。
唯一その同一環境に置かれていないのが、皇族の方々です(婚姻を介して″皇族″となられた女性たちは……と思うにバッシングは目に余る)。勿論、関係性においては国民や制度的影響の「下」に置かれてしまいますが、このことの意味は大きい……と思っています。
(多大なる負担をおかけしますが。ここは大変心苦しい。まさに「なって頂いている」以外あり得ない。)
「聖域性」とは、そんなことをも意味する……と思う次第です。
また、皇室との関係性は「片務的」ではない……ことも国民は忘れてはいけない(理屈上、これは「皇族も」にはなるが、少なくとも現状その心配は皆無。いや、バランスが悪すぎである)。
で、茶谷氏の言説、論考は片務に偏りが過ぎる……ので(彼に限らず)違和感を覚えるのでは?と思っています。
パワーホール
2024年9月1日
政治の暴走を止めるためにも内奏は重要だと思います。そうすれば、政治家も襟を正せると思います。
基礎医学研究者
2024年9月1日
>サトルさん、ただしさん
コメント、ありがとうございました。実は自分、茶谷さん自身のこの記事の見解については、必ずしも同意しません。ただ、今後の皇室と国民の関係を考える上で、記事の意図とは異なり良い題材を提供してくれたと思います。で、紹介には自分の解釈はあえて書かなかったのですが、毎日新聞さんへの意見・コメントにはそれを書きましたので、以下に示します。ご参考までに。
—————–
8/30朝刊の皇室関連記事への意見コメント
8月30日朝刊の4面に掲載されました、須藤孝記者まとめによる「昭和天皇 探った政治関与 動き抑制 納得促した側近」と言う、志学館大学教授の茶谷誠一氏(以下、茶谷さん)へのインタビュー記事を読みました。全体としては、興味深い題材を提供された記事と思いました。
さて、率直な感想をいいますと、須藤記者の最初の1文に反映、すなわち、「象徴天皇制は日本国憲法とともに突然生まれたわけではありません。」と言う部分について、私の理解は少し異なります。でもこれは、須藤記者のまとめがおかしいというよりも、茶谷さんの論の持っていき方に問題があって、まるで昭和天皇さまの“天皇”としてのお振舞が、大日本帝国憲法と日本国憲法の間で断絶しているかのような印象を受けます。おそらく、茶谷さんは昭和天皇さまの戦後のお振舞いをあまり好ましく思っていないのではないか?と推測されましたが、この記事には茶谷さんの意図とは異なり、昭和天皇さまに関する重要なことが書かれています。それは、昭和天皇さまは英国の伝統である“オーディエンス”を志向していた、ということです。この記事の「政治関与」という言い方は、何か天皇が「権力」を担っている、政府や国会に干渉するかのような印象を与えますが、皇室は伝統的に「権威」を担っているのであって、特に昭和天皇さまは、戦前においても安易に政治的な干渉をされたことはなかったはずです。私見では、「権威」を損なわない形での立憲君主としての振る舞いを体現された天皇だったということが、この記事でもよくわかりました。問題があるとしたら、内奏された国民側が、パアっ~と安易にしゃべってしまうことにあるのではないでしょうか?それは最近でも、額賀衆院議長が上皇后陛下に「皇位継承問題」のことを頼みます?ということを安易にもらしてしまうようなこととも、大きな関連があります(否定はされていますが、国民はこういうところは慎むべきです)。でも、オーディエンスは、皇室と国民の関係を考えると、日本の皇室でも是非取り上げたほうが良い制度であり、現在の皇位継承問題のことを考えても、「国民の声」は直接届き、当事者の陛下がどう感じるのか?という場はあったほうが良い、と愚考します。その意味では、今回の記事は、今後の皇室を考える試金石を提供しているように思えます。
最後に、私は激動の時代を生きてきた昭和天皇さまの“戦後の気概”みたいなものがこの記事から感じられたことは、1つ収穫でございました(おそらく、茶谷さんの意図とは異なると思いますが、私はそう感じました)。毎日新聞さんの皇室の記事には、購読者として、今後も期待しています。
ただし
2024年9月1日
とてもとても良い記事でした。どうもありがとうございました!!
やっぱり陛下は、元首、立憲君主、国家というものを、誰よりも分かってらっしゃるのですね。
自分も、小林よしのり先生の「天皇論」シリーズを読んでいなければ、茶谷氏のように、昭和天皇の真意には気付けないままだったかと思います。
サトル
2024年9月1日
非常に興味深い。
ここでも「相思相愛」が重要である。
いや、絶対的に重要です。
「なぜなら」、オーディエンス……内奏……は「国民」からの「声」になり得るからです。
相思相愛ならば。ロシア、フランス、ドイツ、イタリア……王制が廃止になった根本理由はそれがあるかないか。
(どこに目と耳を傾けていたのか?口は誰を意識していたのか?)
この記事の視点は極めて重要です。
いや本当に。