女性天皇・女系天皇をめぐる議論の際、よく男系派が持ち出すのは「女系継承は易姓革命だ」という論理です。 易姓革命とは、簡単に言うと、姓とは父から子へと継承されるものであり、天子の姓が変わることは王朝の交代を意味するという理論です。
その理論から言えば、女性天皇はまだ父から子による姓継承が維持できているが、その後の女系天皇が実現したら、父から子への姓の継承が途絶えてしまい、姓の変更、易姓革命であると男系派は言います。
それに対し、女系・双系派の反論は「易姓革命は大陸の論理であって日本にはない」「天皇にはそもそも姓はないから易姓革命は起きない」「日本はもともとは双系継承」というものでした。
ですが、ここで一歩立ち止まって考えてみたいのは、本当に中国歴代王朝は全て男系継承だったのか?ということです。
本当に、皇族において母から子への継承はなかったのでしょうか。
結論から言うと、一つ、皇位および姓の女系継承が成功しそうになった見つかりました。
中国唯一の女帝・武則天(則天武后)とその直子の睿宗です。
武則天(則天武后)
唐の高宗の皇后となり、のちに宮中の実権を握り、
高宗の崩御後はついに皇帝にまでなって国号を周(通称・武周)に変更した、中国史上唯一の女帝です。
彼女の存在は日本でも有名ですが、
実は息子に対して女系継承による皇位と姓の継承を行おうとしたことはあまり知られていません。
武則天には高宗との間に息子が4人、娘が2人いましたが、
彼女の皇帝即位時にいた息子は中宗(李顯、李哲)と睿宗(李旭輪、李輪、李旦と何度も改名)の2人です。
さて、西暦690年、武則天が皇帝に即位して唐を滅亡させ、武周を建国した(武周革命と呼ばれます)のは前述した通りですが、
その際には自らの子、睿宗を唐の皇帝から武周の皇嗣に変更しました。
そしてその際になんと、睿宗を、唐の皇帝の姓であった李姓から武姓に変更したのです。
睿宗は唐の高宗(李姓)と武則天(武姓)の子です。
姓は父から子に継承されるので、そのままなら李姓となります。
それでは武姓の武則天の建国した武周の皇帝にはなれないのが中国の伝統です。
そこで武姓に変更した上で皇嗣としたのです。 つまり、特別に母親の姓を継承したわけです。
「皇族においても、姓は母から子に継承可能」という先例ではないでしょうか。
文責 東京都 マサノブ
(※編集部より。後編に続きます)

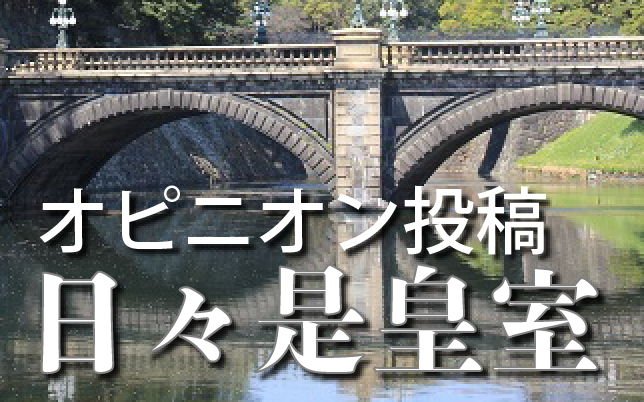
1 件のコメント
くろひょう
2025年2月13日
本来の意味を考えますと、易姓革命という言葉を血統の継承に対して使うことには違和感があります。
姓という一文字があることと、当時は政権の世襲が当たり前だったことからやむを得ないとも思いますが、現代においては大統領交代や与野党交代といった政権交代のほうが、易姓革命という言葉の持つ本来の意味に近いのではないかと思います。