
筆者は先日の「トンデモ説が壺に~」で「日ユ同祖論」を粉砕しましたが、文中に登場した木嶋神社(蚕ノ社:京都市右京区太秦)の三柱鳥居には別の意味がありました。鳥居の中央に立った時、夏至の日の出は比叡山、冬至の日の入りは松尾山となる設計であり、つまり当施設は景教(キリスト教ネストル派)の遺跡ではなく太陽観測所でした。当社の在る太秦は5世紀に新羅から渡来帰化した鉱山技術者(金属の採掘・精製を行う)集団・秦氏の領地でした。太陽観測は海を超えるにも山の位置を測るにも農耕にも重要な技術であり、従って比叡山・木嶋神社・松尾山は秦氏のレイライン(聖地を結ぶ線)だと言えます。ちなみに広隆寺(太秦)は秦河勝が聖徳太子から拝領した弥勒菩薩像を安置した秦氏の氏寺です。
秦氏に関わる他のレイラインとしては、元伊勢内宮皇大神社(福知山市大江町)と崇道神社・御蔭神社(京都市左京区:秦氏と近縁の賀茂氏の聖地)と伊勢神宮(伊勢市)を結ぶ線も有ります。また、天照大神の御霊と八咫鏡は倭姫が大和の宮中から伊勢へ移し、そこに皇大神宮(内宮)が建てられ、元伊勢籠神社(宮津市:天橋立の直近)の豊受大神を外宮に勧請して伊勢神宮は現在の姿になりました。
さて、3~5世紀の日本には丹後・丹波・但馬に跨るタニハ王国が在ったという説が有ります。元伊勢籠神社(宮津市)は彦火明命(饒速日命:邇邇芸命の兄)と豊受大神を祀っていますが、タニハ王家とも言うべき丹波国造家の海部氏は彦火明命の末裔だとされます。先に河内に天下った饒速日命は筑紫に天下った邇邇芸命の子孫(神日本磐余彦=神武)との戦に敗れましたが、本拠地タニハに居た饒速日の子孫が海部氏で、そこに技術者集団・秦氏を伴う新羅王子・天日矛も渡来帰化し、天日矛の子孫と海部氏との婚姻家系の子孫が息長帯姫(息が続く海人族にルーツがある:後の神功皇后)だと考えられます。
息長帯姫の父方は開化天皇(9)、母方は天日矛にルーツがあり、神功皇后の三韓(新羅・百済・任那)征伐は祖先の故国を服属させたことになります。皇后は息子の応神天皇(15)が即位するまで69年も摂政を勤めましたが、大正15年までは神功天皇(15)という扱いでした。「男尊女卑の慣習が人民の脳髄を支配」(井上毅)との理由で外したのでしょうが、「愛子天皇の時代」には戻されるべきだと考えます。
文責:京都のS

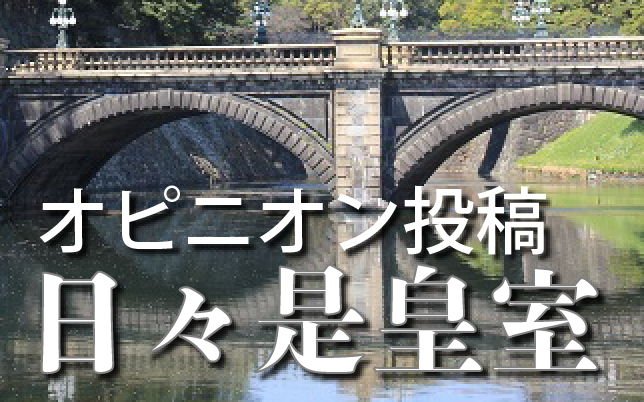
5 件のコメント
京都のS
2025年11月12日
天日矛の渡来帰化が3世紀半ばで、秦氏の渡来帰化が5世紀なら、日矛が秦氏を伴ってきたわけではなく200年ほどのラグがあります。失礼しました。
京都のS
2025年6月20日
任那日本府の成立前なので、三韓は新羅(辰韓)・百済(馬韓)・伽耶(弁韓)でした。
京都のS
2025年6月5日
饒速日命には2人の妻が居り、天道日女命(大国主の娘)との間に天香語山命、一杵嶋姫命(宗像三女伸の一柱)との間に穂屋姫命が居り、その異母兄妹が結ばれて続いていく家系が海部氏(海人族)です。ザ・国津神ですが、権威は有りそうです。このことは女系の血も優先される日本社会に在っては重要です。皇位継承が群臣推挙だった時代ゆえ、開化天皇に大した権威が無いわけですから、女系の血は重要だったはずです。素戔嗚・大国主・新羅王子(天日矛)・開化帝…の血が入った息長帯姫は血統的には申し分なかったはずです。だから「神功天皇」という扱いなのでしょう。
京都のS
2025年5月31日
『ゴーマニズム宣言EXTRA1』の「牛首とスサノオの古代史」でクローズアップされた宗像三女神(アマテラスとスサノオの誓約で生まれた神)の一柱・市杵嶋姫命が彦火明命(饒速日命)の妻です。つまり、神功天皇の勇ましさはスサノオ譲り(市杵嶋姫はスサノオの十拳剣から産まれた)ってことになりますね。
京都のS
2025年5月31日
掲載ありがとうございました。本稿は「トンデモ説が壺に至るバタフライ・エフェクト?」( https://aiko-sama.com/archives/55530 )の続きです。
木嶋坐天照御魂神社(蚕ノ社)にある正三角形(△)の三柱鳥居は、右辺中央と左下頂点を結ぶ線の延長上に比叡山(夏至の日の出)と松尾山(冬至の日の入り)があり、左辺中央と右下頂点を結んだ線の延長上に愛宕山(夏至の日の入り)と稲荷山(冬至の日の出)があり、下辺中央と上方頂点を結んだ線の延長上に双ヶ岡(秦氏を葬る古墳群)があります。
また当地は「元糾の池」と呼ばれ、比叡山方向に伸ばした線の延長上にあるのが下鴨神社の「糺の森」です。「糺す(タダス)」の語源は比叡山から上る朝日が「ただ射す」とのことです。そして賀茂氏と秦氏は近縁の氏族だそうです。