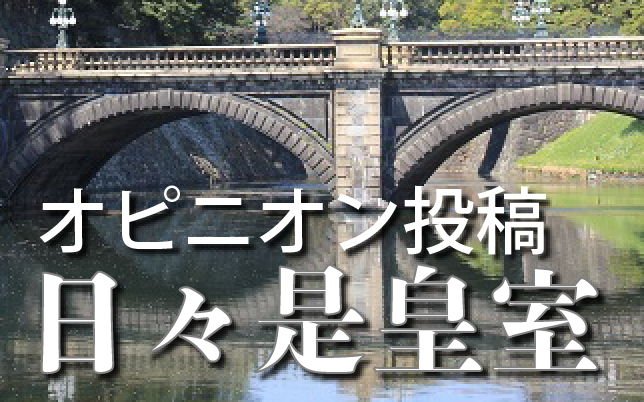民主党 野田政権下に作成された有識者ヒアリングの報告書を読みました。(その経緯は、小林よしのり著 天皇論平成29年 p.499に掲載されています)
皇室制度に関する有識者ヒアリングを踏まえた論点整理(平成24年10月5日 内閣官房)https://warp.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/3754331/www.kantei.go.jp/jp/singi/koushitsu/yushikisha.html
論点が一代限りの女性宮家と分かっていたものの、、嘆息が漏れます。
報告書の一部を抜粋し、ハイライトと図で表示します。
興味がある方は、お時間あるときに<(_ _)>
4項:検討に当たっての基本的な視点
今回の検討に当たっては、男系男子による皇位継承を規定する皇室典範第1条には触れないことを大前提とする必要がある。
⇒ 前提から間違えているので、答えも間違えることになります(後段)。
5項:具体的な方策
(Ⅰ)女性皇族が婚姻後も皇族の身分を保持することを可能とする案
(Ⅱ)女性皇族に皇籍離脱後も皇室の御活動を支援していただくことを可能とする案
⇒ 令和有識者会議は、これを踏襲した二番煎じでした。
(Ⅰ)案は、以下の二案に分かれています。
(Ⅰ―A)配偶者及び子に皇族としての身分を付与する案

・配偶者や子にも皇族の身分は付与されるが、子は婚姻により、皇族の身分を離れる。
・将来の女系天皇誕生につながるおそれがあり、男系男子で125 代継承してきた皇室の伝統を破壊するものではないか。
・歴史的に見て、宮家の役割とは、皇位継承資格者を確保し、皇位継承の危機に備えるものであって、皇位継承資格を有しない女性皇族を当主とする宮家には、意義がないのではないか。
・配偶者にとって皇族の身分となることは、逆に負担になるおそれもある。
⇒ 一代限りの女性宮家の目的は、女系男子・女子の排除と断絶。
女性宮家に反対する常套句は、この報告書が用意したものでした。
(Ⅰ―B)配偶者及び子に皇族としての身分を付与しない案

・配偶者の身分については、一般国民とする方が、女性皇族の配偶者の婚姻に対する負担感、不安感を軽減できるとの見方もある。
・配偶者や子の職業選択の自由等の諸権利については、その身分を一般国民とする以上、法的な制限の対象となるものではないが、その行動が女性皇族の皇族としての品位や政治的中立性に重大な影響を及ぼすような場合には、むしろ当該女性皇族の皇籍離脱の要否の問題として議論されるのではないかと考えられる。
⇒ 一般国民の配偶者が問題を起こした際に女性皇族が連帯責任で皇籍離脱するのなら、配偶者の負担感・不安感は軽減どころか増加する一方です。一般国民の社会権や信教の自由が制限されるのは違憲で、それを予防できる適切な措置は存在しません。
(Ⅱ)女性皇族に皇籍離脱後も皇室の御活動を支援していただくことを可能とする案
・女性皇族が婚姻により皇族の身分を離れた後も、「内親王」などの称号を引き続き保持しながら、皇室の御活動維持に協力していただくこととする案(いわゆる尊称保持案)が複数の有識者から提案された。
・皇族の身分を離れた方がこれを称号として保持できることとする規定を同典範に新たに設け、その方に特別の待遇を施すことは、皇族という特別な身分をあいまいにする懸念があり、法の下の平等を定めた憲法第14 条との関係においても疑義を生じかねないことから、本案をそのまま実施することは困難と判断せざるを得ない。
・他方、女性皇族に皇族の身分を離れた後も皇室の御活動維持に引き続き御協力をいただけるような環境整備に努めていくことは重要と考えられ、(中略)その際、公的行為その他の行為を支援するのにふさわしい称号の保持ということについてのみ言えば、女性皇族の婚姻による皇籍からの離脱に際し、「皇室輔佐」や「皇室特使」などの新たな称号を、御沙汰により賜ることは考えられないことではない。
・皇族数の減少に歯止めをかけることはできない。
⇒ 象徴天皇を都合よく利用するところに虫唾が走ります。
女性皇族の皇籍離脱は適法なので、立憲君主の象徴天皇が御沙汰(ごさた:天皇の指示・命令)によって、新たな称号を生みだす必要性がありません。皇族数の減少に歯止めがかからないなら、なおのことです。
6項:終わりに
今回の検討では、皇室の御活動維持の観点から、緊急性の高い女性皇族の婚姻後の身分の問題に絞って議論を行ったが、現在、皇太子殿下、秋篠宮殿下の次の世代の皇位継承資格者は、悠仁親王殿下お一方であり、安定的な皇位の継承を確保するという意味では、将来の不安が解消されているわけではない。安定的な皇位の継承を維持することは、国家の基本に関わる事項であり、国民各層の様々な議論も十分に踏まえながら、引き続き検討していく必要がある。
⇒ 野田政権の最期の抵抗が赤字部に表れていると思いますが、一代限りの女性宮家にまで後退したことは残念です。
この有識者ヒアリングに関しては、7月12日『よしりん・ぽっくん夏祭り』に登壇する 森暢平 成城大教授の記事に、詳述されています。
12年の女性宮家議論は一体どこへいったのか
https://weekly-economist.mainichi.jp/articles/20241029/se1/00m/020/001000d
皇統問題は継続審議されていますが、この報告書に、皇族には認められていない養子縁組案と、皇統に属する男系の男子を法律により直接皇族とする案を追加したものが、令和3年有識者会議報告書です。
平成17年報告書→平成24年報告書→令和3年報告書と、時代が進むにつれて見識や論理が劣化・逆行している事実に、皇室の皆さまは、さぞ落胆したことでしょう。
5月15日の読売新聞社提言は自民党などの男系カルトに大打撃を与えましたが、与野党協議の決着は見えていません。
立民 野田代表、馬淵議員のこれまでの健闘は素晴らしかったですが、愛子天皇(直系継承)を打ち出すことを避けて女性宮家創設から進めようとしている気配があります。
立法の総意に焦るあまり、一代限りの女性宮家などの妥協点に着地しないよう、愛子天皇こそが安定的な皇位継承の最短距離であることを理解頂きたいです。
文責 茨城県 ダダ
(40代男性 麻生や玉木は完全にアレだと理解した派)