森先生のこれでいいのか「旧宮家養子案」第13弾です。
男系より直系が、皇位継承の本質原理です。常識的に考えても、娘がいるのに、みたこともない遠い親戚のおじさんを跡継ぎにしないですよね。天皇家においても、もちろんそうした原理がありました。これでいいのか旧宮家養子案第13弾です。https://t.co/ZoqlHtm8Bi
— 森暢平 (@mori_yohey) April 16, 2024
Web記事はこちらから
サンデー毎日:「男系」より「直系」が皇位継承の本質原理だ 社会学的皇室ウォッチング!/111 成城大教授・森暢平
過去に8人いた女性天皇のうち最後の即位は、江戸中期の後桜町天皇である。彼女は幼少の甥(後桃園天皇)の即位までの「中継ぎ」だと語られることが多い。しかし、彼女が女帝となった経緯をみると興味深いことが分かる。それは、皇位継承原理の本質は実は男系よりも直系が重視されていたことだ。
と始まる今回。
男系より直系
「女性天皇中継ぎ説」って改めて何だろう。後付けじゃないかと感じています。
桃園天皇が21歳で突然亡くなりました。突然亡くなったので後継者が誰とも決めておらず(勅定がなく)、第一皇子の英仁親王(4歳)がいるものの、桃園天皇の姉である智子内親王が御桜町天皇となる。
森先生は
この措置は前例にも伝統にも則(のっと)っていなかった。
と書いています。
森先生は、近世史研究の野村玄の著書を例に挙げ、
男系優先ならば、そのまま第一皇子に継がせるか、中継ぎ候補になる宮家の男系男子が実際にいた。
(閑院宮典仁(すけひと)(29)、京極宮公仁(きんひと)(29)、有栖川宮職仁(よりひと)(48))
にもかかわらず、御桜町天皇が誕生したのは、英仁親王が幼くして亡くなってしまうと、「中継ぎ」であった血縁の遠い宮家が中継ぎでなくなってしまうことを防ぐ目的での御桜町天皇即位。この即位に宮家は反発したが、
森先生はこう書いています。
こうした経緯から分かることは、皇位継承で最も重要だったのは直系相続であることだ。皇位は、桃園天皇の子どもへとつないでいくという原理である。裏を返せば、男系でつながっているだけで実は系統が遠い傍系には、皇統を移したくなかった。
男系でつながっているだけで実は系統が遠い傍系には、皇統を移したくなかった。
現在男系固執派の皆さま。よく見てください。これが歴史の真実です。
実際に上皇さま、陛下、秋篠宮さまから「旧宮家の養子をとってでも男系でつないでほしい」という意味にとれる
おことば、ふるまいは過去にありましたか?私は見たことがありません。
歴史から見てもしっくりします。
そして森先生は
現在、旧宮家復帰案を唱える人たちは、男系継承だけが皇位継承の伝統と考えている。だが、直系継承こそがより本質的な原理であるという近世史家の指摘は重要である。その原理で言えば、悠仁さまより愛子さまへの継承のほうが、より近世の伝統に近いということになるだろう。
愛子さまを皇太子に
これが伝統に近い形です。
「中継ぎ天皇」と言われますが、その後73歳で亡くなるまでの43年間、上皇として、後桃園、次々代の光格天皇の後見役を果たされます。
これだけでも「中継ぎ」ですか?
沢山の和歌を残し、直系から遠い光格天皇(詳細はこちら)へ、天皇としてのあり方を伝え続けた御桜町天皇。
光格天皇は「男系男子だから」誰の手も借りずに天皇が務まったのでしょうか。
中継ぎなんて失礼じゃないか!
森先生は結びに、
後桜町天皇の聡明さは、現在の愛子さまを彷彿(ほうふつ)とさせる。女性だから皇位に就けないというのは日本の伝統ではない。女性だからこそできることもあると後桜町の生涯が教えてくれる。
「女だから」愛子さまは皇太子になれない。
「男系男子しか天皇になれないのが伝統だ」
こんなバカバカしい「ホシュごっこ」はもう終わりにしましょう。
日本国に何もメリットがありません。
国会議員はよく勉強しなさい。国民の側から盛り上げてやります。
森先生の次回作、ますます期待します。
今回は最後に、森先生が「すごい」とポストしたものを紹介して終わります。
これはすごいと思いました。私の複雑なお話を、ワンセンテンスで要約してくれている。目にウロコ。 https://t.co/QBJU04gYG1
— 森暢平 (@mori_yohey) April 17, 2024
文責 愛子天皇への道サイト運営メンバー ふぇい

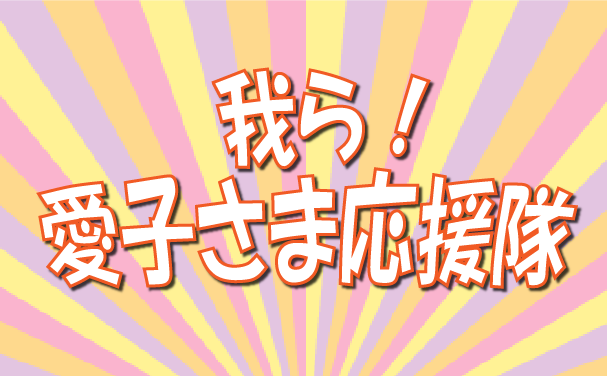
4 件のコメント
くりんぐ
2024年4月21日
天皇の歴史で「中継ぎ」と言われた方は、後継者と予定されていた方とは1親等〜2親等と血筋の近い親族でした。
元明天皇は聖武天皇の祖母、元正天皇は聖武天皇の伯母、白河天皇は実仁親王の兄、後白河天皇は二条天皇の父、後西天皇は霊元天皇の兄。
そして後桜町天皇は後桃園天皇の伯母。
「血筋の近さ」が重要視されていたことがよく分かります。
男系派は「男系で繋がってるなら、どれだけ離れていても皇位を継げる」と思い込んでるようですが、実際には血筋が離れれば離れるほど「皇統交代」と見なされていたので、誰でもいい訳がなかったのです。
5親等〜7親等で駄目なら、それ以上に血筋が離れている旧宮家系国民男性は論外ですね。
「女系で近い方がいる」と反論してくるでしょうけど、女系を否定する奴が言うなという話です。
後桃園天皇が成長されるまでの中継ぎに選ばれたのは、世襲親王家の親王たちとは違って後桃園天皇と血筋の近い後桜町天皇でした。
後桜町天皇は、後桃園天皇の教育に熱心に取り組まれ、その後桃園天皇が若くして亡くなった後は、その娘婿として閑院宮家から迎えた光格天皇の教育に熱心に取り組まれました。
「次の世代に“天皇の役割”を繋ぐ」大役を、後桜町天皇は見事に果たされたのです。
今上陛下の直系である愛子さまは、今上陛下のもっともおそばで、「天皇のあり方」を学ばれてきました。
その愛子さまなら、きっと「天皇という大役」を担うことができます。
過去の女性天皇たちが、「天皇という大役」をまっとうされてきたように。
キケロ
2024年4月19日
元の記事も併せて読んでみましたが、
「こうした経緯から分かることは、皇位継承で最も重要だったのは直系相続であることだ。皇位は、桃園天皇の子どもへとつないでいくという原理である。裏を返せば、男系でつながっているだけで実は系統が遠い傍系には、皇統を移したくなかった。」
少なくとも英仁親王がいる時の段階では、あくまでも「正統(しょうとう)」は中御門皇統なので、記事にあるように「直系相続」を考えおり、「男系でつながっているだけで実は系統が遠い傍系には、皇統を移したくなかった。」はずです。
しかし後桃園天皇が在位中に崩御した後は、世襲親王家から養子を迎えることになります。
つまり皇統を移しています。
世襲親王家は記事にあるように三家ある中で、世襲親王家の創設が一番近い閑院宮家、さらに出家していない親王として、祐宮(後の光格天皇)を養子に迎えています。
光格天皇の中宮は後花園天皇の第一皇女である欣子内親王であり、温仁親王や悦仁親王の男子を出産するものの、夭折したため中御門皇統は女系としても残らなくなってしまいました。
ちなみに世襲親王家の創設が古くなればなるほど、「正統」から外される天皇が増えてしまうので、それを選択するのは難しいと思います。よく言われる旧11宮家の母体となる伏見宮家から養子を迎え入れて、その人が天皇になるとすれば、室町時代の後花園天皇以降の天皇が「正統」ではなくなるため、それを考えていたとは思えません。
また後桜町上皇を始め、摂家などの公家がそれを容認するとも思えません。
あとなぜ後桜町天皇が女帝として立てられたのかといえば、やはり中御門皇統を「正統」として維持するためです。
またなぜ幼帝の先例があるものの、英仁親王の即位ではなかったのかといえば、おそらく院政を行う院がいなかったためだと思います。
桃園天皇の時に院政を行ったのは先代の桜町天皇であり、桜町天皇はすでに崩御しいます。桃園天皇も若くして崩御したため、宮中において後見となる院が必要だったのではないかと思います。
後桜町天皇は記事にあるように聡明な女帝であり、光格天皇が英邁な君主になったのも後桜町天皇がいたからこそです。そういった意味では、昨今のように女帝を単に「中継ぎ」と見なしてしまうのは君主としてのありようを見失ってしまうでしょう。
SSKA
2024年4月17日
男系には独身女性以外は穢れるとの馬鹿な考えがある為に過去の女帝は議論中の女性宮家や女系の先例とはならないと主張します。
こんな差別観念を立民のまともな人以外、女性を含む大勢の議員が制度化しようとしているのは狂気としか思えません。
サトル
2024年4月17日
森暢平氏の連載は、毎週愛読しています。驚くと共に、感動すら覚えます。
なんだろう……「そうだ!やっぱりそうなんだ!」と、力強いエール?を感じます。
個人的な願望ですが、7月の「祭り」に、是非とも森氏にも、来場してほしい、登壇して欲しい!と熱望すると共に、毎日新聞社の「田中裕之記者」にも取材に訪れて欲しい!と、こちらも熱望する次第です。いや、田中記者、社説を書かれた論説委員の方には、今すぐにでも!です。