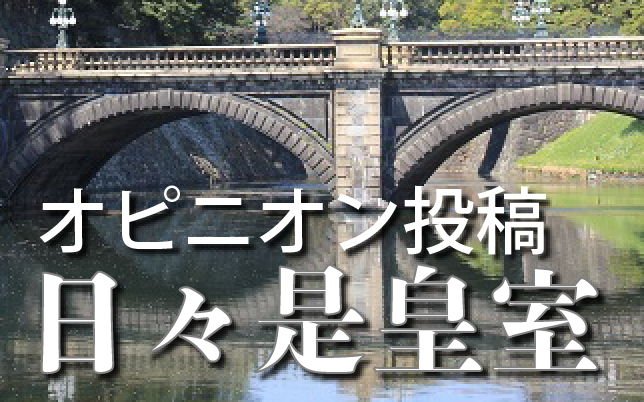※前編はこちら中国(唐)にもあった。皇室と姓の女系継承、そして直子優先の原則。女系継承は「易姓革命」ではない(前編)
その後に武周に起こったエピソードも特筆に値します。
それは直子優先の原則が示されたということです。
さて、前編で示した通り、武則天の後継者たる皇嗣は睿宗こと武輪に決まったわけですが、やはり睿宗は元は唐王朝の李氏の人なので、
生来の武氏の人からすれば自分たちこそ真の王家、という意識があったのでしょう。
武則天の甥である武承嗣と武三思の2人が、睿宗は元は異姓なので武姓である自分達をこそ皇太子に、という運動を起こしたのです。
武則天の心にも迷いが生まれたようです。これに対して、武則天の右腕だった宰相・狄仁傑はこう意見を上申しました
「叔母甥の関係よりも親子の関係の方が深い」
「実の子を後継者にすれば、はるか先まで祭祀を継いでくれ、子々孫々まで承継される」
「甥が天子となって叔母を廟に祀ったなどという例はない」
そして、武則天の夢の解釈を通じて、実子である2人の息子を取り立てることを説いたのです。
武則天はこの意見を受け入れました。
皇位継承における直子優先の原則がここに示されています。
このまま武周が安泰に続いていれば睿宗こと武輪が皇位を継承し、女系による皇位の継承が先例として残ったかもしれません。
残念なことに史実はそうはなりませんでした。
民衆の唐への支持は根強く、革命を断行した武周への反発は強かったのです。
皇太子の座は睿宗から中宗へと変更になり、睿宗は李姓へ戻ってしまいます。
そして数年後、武則天の崩御前にクーデターが勃発し、武周は倒され唐が完全に復活するわけです。
(余談ですが、睿宗はその後再び皇帝に即位しました。唐の皇帝から武周の皇嗣となり、また唐の皇帝となった奇妙な経歴の持ち主です)
なので、武則天の先例はあくまで一時的なものではありましたが、それでもこの故事からわかるのは、
男系男子継承と易姓革命の本場である中国の唐王朝においてさえも、
女帝から子への皇位継承の際には、「母から子への姓の継承(姓変更)」という形で母子継承が実現されようとしたこと。
生まれつき同じ姓の甥よりも、後から姓を変更した直子が優先という原則が説かれていたということです。
日本では、皇室における姓の存在自体を否定する人が多いでしょう。
ですがたとえ一部男系派のいうように「姓」の概念が日本の天皇にあったとしても、
母である皇族女性から子に対して、武則天と睿宗(武輪)のように姓を継承できている、と考えてしまえば良いだけです。
出典 中国古典文学大系14「資治通鑑選」 頼惟勤・石川忠久 編 平凡社
文責 東京都 マサノブ
※編集部より、引用はこちらのX画像をご覧ください。
唐の武則天(則天武后)は唐を廃して周を建国したが、その際、自分の子である睿宗に、自分の「武」姓を与えて皇嗣とした(姓の女系継承)
— マサノブ (@Great_Masanob) February 11, 2025
また、甥の武承嗣、武三思が我らこそ武姓の本流、と皇位継承を主張すると、武則天の片腕の狄仁傑は「甥より直子が継承するのが相応しい」と説く#愛子さまを皇太子に pic.twitter.com/LmAj6rfg70