天下統一目前の曹操と呉の孫権・劉備が開戦し、 互いに智謀の火花を散らします。
呉の総司令の周瑜と劉備軍の軍師・孔明は曹操のスパイを上手く利用して、曹操の水軍の主力、水上大要塞を指揮していた、劉備をいじめ、亡き主君の意を反して曹操に降った蔡瑁を殺させ、水上大要塞を使えなくします(ここまで前回のあらすじです) 。
*今回は皇室の話題はまったくでてきません。ここでは、やや強引ですが、孫権・劉備≒尊皇、曹操≒佐幕、と置き換えて読んでいただければ、また味わいもあるのではないかと(by基礎医)
曹操軍は水上大要塞使えなくなるも、まだ大軍を率いている状態で、呉の水軍をもってしてもまだ勝算がつかない状態でした。 演義では、 周瑜は孔明と話し合い、何か良い手がないか考え、閃いた様子で、孔明に 「良い案が浮かんだが、ちょっと不安なんだ。」 と言い、孔明も 「私も良い案を浮かびましたよ。」と応えます。 周瑜はお互いの手のひらにその案を書いて互いに見せよう!と持ちかけ、孔明は涼し気に了承し手のひらに文字をかき、一斉に見せあい、そこには 「火」とありました。 それを見て互いにフフッと笑います。
大軍を叩きのめすには火攻めが効果的であり、敵が不慣れな水上で船がおぼつかないところに火が燃えたら、混乱強く、あわよくば同士討ちに出来ると2人は考えました。
周瑜は最初喜ぶも、やっぱり孔明は危ないと、また孔明の暗殺を頭によぎらせます。 そこへ魯粛が周瑜達に曹操軍から先の曹操に首を跳ねさせた蔡瑁の弟・蔡中が呉に投降してきたと知らせました。周瑜達が蔡中に会うと、蔡中は無実の罪で曹操に兄が殺され、仇を討ちたく投降したいと切々と訴えます。周瑜はそうか、そうかと彼の投降を受け入れました。 無論、これは曹操の計略ですが、周瑜達は利用しようと泳がせます。
周瑜はこの蔡中をどう使おうか思案してると、呉の古参武将の黄蓋(こうがい)が自分を使ってくれと申し出て、周瑜は黄蓋とある策を練ります。 翌日、周瑜は軍議をして方針を指示したさい、黄蓋は「若造の言う言葉なんか聞けるか!」と啖呵をきり、反抗します。 周りがどよめく中、周瑜は傲慢不遜である!と黄蓋を棒たたきにしてめった打ちし、黄蓋を下がらせ、黄蓋は「若造、覚えてろ!」と気絶します。 そんな中、蔡中はこれは”チャンスだぞ!”と目を輝やかせ、傷だらけの黄蓋に見舞いにいき、囁きます。”曹操のもとに来ないか?”と。 黄蓋は”かかったな!!”と目を一瞬光らせ、 “是非に曹操に会いたい!”と蔡中に頼みます。 蔡中は”してやったり!”とほくそ笑みました。 しかし、策にはまらせたのは周瑜達です。 君主の為に戦いに勝つ為には味方を騙し、敵を騙す事も必要です。
周瑜は魯粛に”今度こそ孔明より上手く計略したぞ!孔明も戸惑っていた!”と嬉しそうに語り、 魯粛は周瑜をみて、 “孔明が知らないはず無かろうに。”と複雑な様子を見せます。 周瑜は孔明恐れに足らず!と孔明を陥れる計略をしかけます。 周瑜は軍議で孔明に、「火攻めに何が必要でしょうか?」と問い、孔明は「矢ですね。」と答えます。 周瑜はすかさず、「どのくらい必要と思われるか?」と尋ね、孔明は少し思案して 「10万本あると良いですね。」と答えると、 周瑜が準備に幾日かかる?1週間で出来るか?と重ねて問うと、孔明は「1週間なんて悠長な。三日で十分です!」とはっきり言います。 周瑜は「軍議で戯言は御法度ですぞ!」と凄むと孔明は大丈夫、大丈夫!とにこりと笑います。 さらに孔明は”三日で用意出来なかったら、この首をあげます。”と周瑜に誓います。 周瑜は街の工房全てに、孔明から矢を作れと言われたら全て断れと御触れを出して孔明を鼻で笑います。
魯粛は孔明を心配して訪れると、孔明は飄々と魯粛を小舟で舟遊びを誘います。魯粛は魯粛で冷や冷やし、孔明に”遊んでる場合か!”と詰め寄ると、孔明はニコニコして”今から矢を貰いに行きます”と小舟を出します。折しも夜に霧が濃く出ており、孔明は魯粛に、霧に乗じて矢を貰うため、藁人形達を乗せた小舟をもう10艘つけてもらいました。
魯粛と孔明が曹操のもとに向かうと、丁度矢が届く範囲まで霧が濃く、孔明はサッと羽扇にて各舟に銅鑼を鳴らせと合図を送ります。 一方、曹操軍は突然の銅鑼の音と霧の中の小舟を軍船と思い、迎え撃ちます。
今回はここまで。 (三国志編その10、赤壁編その6)に続きます。
次回は敵軍に味方あり、孔明の友達徐庶と鳳雛が活躍します。
文責 神奈川県 神奈川のY

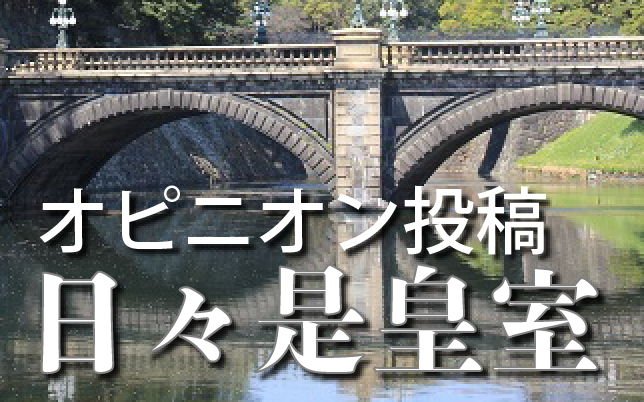
5 件のコメント
神奈川のY
2025年3月24日
あしたのジョージさま、コメントありがとうございます。孔明が矢を集める場面は赤壁の戦いの見どころの一つなので間違いないですよ。史実ではないみたいですが、演義の方が面白みがあるのでずっと語られてるのだと思います。
あしたのジョージ
2025年3月24日
京都のSさんの後からでは書きにくいですが、孔明の矢を集める話、映画のレッドクリフにもあったような気がしました。
勘違いかもしれませんが、なんとなく思い出しました。
なんにしても孔明は人の裏の裏の裏を常に考えているような非常に頭がキレるイメージですね~🤔
神奈川のY
2025年3月24日
京都のSさま、基礎医さま、コメントありがとうございます。
京都のSさま、
毎回観て頂き、ありがとうございます。
今回の話ですが、尊皇と関わりが中々難しいところでコメントしずらくして申し訳ないです。赤壁の戦いで語るには外せない場面でしたので基礎医さまにお手間かけて頂きました。また、尊皇と佐幕に対しての見解分かりやすく教えて頂き、ありがとうございます。
基礎医さま、
編集いつもお手間かけて頂き、ありがとうございます。
尊皇に必要な駆け引きのヒントと分かりやすく書いていければと思います。
基礎医学研究者
2025年3月24日
>京都のSさん
ありがとうございました。いやいや、尊皇の対義語として”佐幕”を安易に使いました。これは、神奈川のYさんの意図とはまったく関係なく、底の浅い用い方をしましたことを、お詫びします(ここでは、非尊皇が適切だったと思います)。そして、なるほど、勉強になりました。たしかに、こうやって整理してもらえると、尊皇⇔砂漠という単純な図式ではありませんね。ありがとうございました。
京都のS
2025年3月24日
毎回、読み物としては非常に面白いのですが、コメントしにくいとも感じていました。今回はナビの基礎医さんから「やや強引ですが、孫権・劉備≒尊皇、曹操≒佐幕、と置き換えて読んでいただければ、また味わいもある」とアナウンスされたので、これについてだけ反応します。
以前から私は、幕末の対立が尊皇攘夷派VS佐幕派とされてきたことに強い違和感を持っていました。佐幕の反対は倒幕、攘夷の反対は避戦、開国の反対は鎖国、尊皇の反対は非尊皇としか言いようが無いからです。
薩長を尊皇派と規定した場合、反対側の水戸や会津や幕府は非尊皇か?と言えば、水戸と会津はガチ尊皇、幕府も将軍の権威を担保する意味では尊皇です。逆に薩長は幕府から権力を奪取するために天皇を政治利用(岩倉具視が捏造した「錦の御旗」が好例)したのですから尊皇とは呼べなくなります。
以上を前提として再分類すると…
・幕府守旧派:佐幕・避戦・鎖国→開国・尊皇
・幕府開明派(勝麟太郎・小栗上野介):佐幕・武備→攘夷?・開国・尊皇
・水戸&会津:佐幕・攘夷・鎖国・尊皇
・薩長土肥:倒幕・攘夷・鎖国→開国・尊皇?
こうなってくると薩長と幕府側との対立点は倒幕か佐幕かだけです。つまり戊辰戦争とは、英仏の代理戦争として倒幕派(英)と佐幕派(仏)が戦っただけだとしか言えなくなります。さらに、薩長が孝明天皇(公武合体派)を排して明治天皇(傀儡の幼帝)を立てた点を重視すれば、薩長こそ非尊皇で、孝明帝を支持した徳川慶喜や幕臣たちこそ尊皇派だと言うことも可能です。
2027年の大河「逆賊の幕臣」は小栗上野介忠順(松様桃李)が主人公です。「倒幕派か佐幕派か、一体どちらが逆賊だ?」といったことにも注目しながら、私は再来年の大河に臨みます。ちなみに惟任びいきの私は「豊臣兄弟!」(2026)を無視します(笑)。
済みません。思いっきり関係のないコメントでしたね。漢の再興を目指す劉備が尊皇で、漢を滅ぼして自分が成り代わりたい曹操が非尊皇なのは解りますが、「え?佐幕?」となったので書いてみました。