古今東西、小国が大国相手に戦う事があるさい、 小国はどう戦うのか、今でも問われている事かと 思われます。 三国志時代の大陸を半ば制した曹操の大国、 天下統一の為、豊富な物資、兵力をもとに従わない小国、呉の孫権と、まだ国と呼べないながらも 国の再興を諦めない劉備を曹操が戦を仕掛けます。孫権も劉備も君主として自国を護る為、臣下達と一致団結し、戦略・謀略を駆使します (ここまで前回のあらすじ含みます) 。
*この連載は長期にわたるため、今回のように「皇室の話」が直接でてこないこともありますが、(帝を中心とした)国を再興する、あるいは、君主と臣下の物語としてみていただければ、幸いです(by基礎医)
曹操は豊富な物資と兵力、それから必勝と呼べる 策を龐統から授けられ、さらに呉の古参武将・黄蓋のお土産付きの降伏の知らせに意気揚々となります。あまりの曹操の意気揚々さに曹操の軍師達は危惧し、万が一の備えを進言するも、人形劇三国志では、「戦は大きな賭けじゃ!万が一起こることまで心配していては戦ができん!」と退け、戦前に豪勢な宴を開いて歌を詠みます。元歌はこんな感じです。
以下歌文。
對酒當歌 人生幾何
譬如朝露 去日苦多
慨當以慷 幽思難忘
何以解憂 惟有杜康
(意味) 酒を前にしたら大いに歌うべきだ! 人生がどれほどのものだと言うのか。 たとえば朝露のようにはかないものだ。 過ぎ去っていく日々は、あまりに多い。 気分が高ぶって、いやが上にも憤り嘆く声は大きくなっていく。 だが沈んだ思いは忘れることができない。 どうやって憂いを消そうか。 ただ酒を呑むしかないではないか!
曹操軍100万対孫・劉備軍10万足らずの戦であり、多くの人は、誰がどう観ても孫・劉備の勝ち目がない戦に見えます。 一方、呉の周瑜と劉備の軍師・孔明は龐統を使い、反間の計(スパイ工作)・連環の計(連鎖して被害を大きくする計略、イメージ的にピタ◯ラスイッチの様な感じの様な。)、そして水軍の練度を上げ開戦の準備を整えました。
しかし、あともう一つ、この条件があればと思う事がありました。それは”東南の風”です。 火攻めに大事な風向きがまだ周瑜達に味方をしていません。演義では戦の気負いと東南の風が吹かない現状を憤り、周瑜は吐血して倒れこんでしまいます。孔明は陣中見舞いに魯粛と共に行き、 “東南の風を必ず吹かせる”と約束しました。 周瑜は孔明に何か算段があっての事だろうと任した後、一方でこの戦で孔明は利用し尽くしたと判断し、後々の憂いとなる孔明を殺そうとします。 魯粛は周瑜から”孔明を東南の風を吹かせたら、殺そうと思う”と聞き、内心”またか!?”と思いながら周瑜と孔明の中を行き来します。
孔明は天気を読み、近隣の民から東南の風が吹くタイミングがあると聞き出し、準備をします。そして、演義では周瑜に、”自分は天気を操る方法を知っているので、祭壇を築き、天に祈り、東南の風を吹かせてあげましょう!”とし、戦の開戦のタイミングと自分が上手く去れるタイミングを築きます。 また、人形劇三国志の孔明と周瑜の会話に、”天に不測の風雲あり、人に旦夕(たんせき)の禍福あり”という言葉が出て来ます。 意味としては、大きな天空でさえ思いがけぬ嵐や雨雲に覆われることがあるのだから、まして小さな人間は短時間のうちに不幸や幸運を繰り返すものである、とあり、 戦の必勝の理には時(タイミング)・地(状況把握・環境づくり)・人(味方の連携)があると言われたそうで、曹操も周瑜や孔明も肝に命じてるところではありますが、人(味方の連携)が一番難しく、理だけでは上手くいかず、人は情で動くもので、計算が出来ないところでもあります。 才知があり、妥協を許さない周瑜と才知があり、頭の中をフル回転して国と君主、自分を敵・味方から護る孔明ですが、この2人の弱点は共通して 人(味方の連携)が上手くいかないところでしょうか。2人だけで戦っていたら恐らく曹操が勝っていたかもしれず、曹操は敵の不和のニオイには敏感で謀略でねじ伏せるのが大好きな御仁ですので2人には大敵でした。
そこをカバーして人の和を保ち続け、曹操に付け入る隙を与えなかったのが、魯粛でした。演義ではお人好しで孔明と周瑜の間を行き来する印象のある魯粛ですが、実は剛柔併せたバランスのある影の実力者、縁の下の力持ちだったと推察します。
話は戻り、孔明は戦の開戦と逃げの最高のタイミングを計り、東南の風を吹かせて姿を消します。 そして、周瑜は曹操に突撃の号令を発し、勝ち戦の夢を観ていた曹操軍に突っ込んでいきます。
今回の話はここまで。次回は赤壁の熱い戦いをご紹介します (三国志編その13、赤壁編その9)に続きます。
文責 神奈川県 神奈川のY

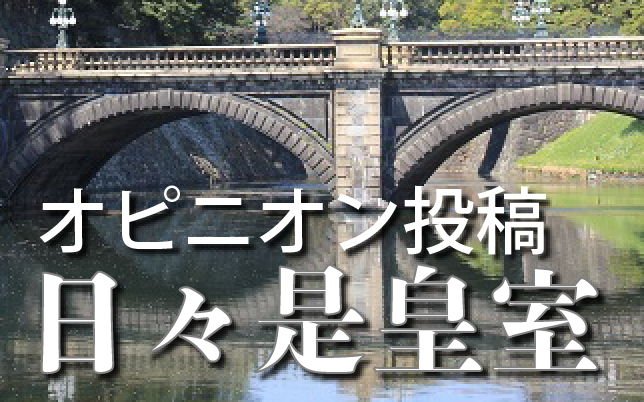
5 件のコメント
神奈川のY
2025年4月13日
皆々様、コメントありがとうございます!
・基礎医さま、改めて三国志を観ると、違った視点で新しい発見がありますね。孔明と周瑜の弱点とか、魯粛のバランスの凄さとか新たに思えました。孔明は才知が抜群ですが、如何せん、人を観る目が狭い感あります。(馬謖と魏延の扱いとか。)司馬懿も曹操の中で揉まれながら才知を発揮してたので侮りがたしです。また、劉備が君主だったから、孔明が主役をはれたとも感じました。水魚の交わり、大事ですね。
・ただしさま、三国志は色々な媒体があり、昔から楽しめるモノの一つです。ぜひ沼って楽しんで欲しいです。三国志演義は外交・戦争・逸話・英雄、君主、武官・文官の立場を感じられる逸品です。
・あしたのジョージさま、”戦は数ではありません、兵法によって勝つのです。”という台詞が良く三国志演義では出て来ますが、
日本でも家康が人質時代に子供の合戦ごっこを観て、配下に「多勢と少数、どっちが勝つのでしょうか?」と問われたさい、
「少数の方が一致団結して事に当たるから強い。逆に多勢だと数に頼んで慢心してるから弱い。」と言ったとか。少数精鋭は強いですね。剣部隊も敵機がでっかく高性能で数が多い相手に殴り込んでは叩きのめしてたし、です。また、孔明は食えない性格もありますので、タイミングを逃さず対応します。周瑜にない強かさかと。
・パワーホールさま、そうですね、丁度来週の議題に合う場面になりました!
武田と毛利の同盟、面白そうですね。どんな戦になるか、ワクワクしてしまいます。
信長と家康は戦国時代の良いタッグだったと思いますので良い勝負してくれるかと思います。
パワーホール
2025年4月13日
国の戦いの話ということもあり、来週開催のゴー宣DOJOのテーマに沿って非常にタイムリーに感じました。
余談ですが、日本の戦国時代に毛利元就と武田晴信が同盟を組んでいたら面白かったと思います。どちらも清州同盟(織田と徳川)から敵視かつ脅威とされておりちょうど清州同盟の勢力圏の両端にいたので挟撃できた可能性があると考えています。
あしたのジョージ
2025年4月13日
人数の差で絶対に勝てると思い込んでいる曹操ですが、孔明と曹操の知恵の差で勝ち目は変わって来るかもしれないので、油断大敵ですね。
必ずしも言える事ではありませんが、最後まで諦めなければ何かいい結果に結びつく事もあるかもしれません。
また命を狙われていると知った孔明は、開戦と逃げのタイミングを計って姿を消すなんて流石ですね~
続きを待ちます。
ただし
2025年4月13日
初めて読み、三国志もほとんど知りません(昔のジャンプで本宮ひろ志のものを少し)が、面白く、次の展開にワクワクしました。国を統べること、人心をつかむこと、戦いに勝つことなどを学べるのかな、などと考えています。
初三国志、あまり
基礎医学研究者
2025年4月13日
(編集者からの割り込みコメント)今回もありがとうございました。ここから、赤壁の戦いの戦場の話に突入ですね!で、個人的には、今回、魯粛をとり上げていただきき、ありがたい。どうも、演義は、特に赤壁の戦いでは孔明や周瑜を持ち上げすぎて、魯粛がお人よしで2人の間で翻弄される姿ばかりが目立つのが、少し不満でした。
神奈川のYさんの描き方は、史実の魯粛に近く、自分ももし魯粛が呉にいなければ、孫権は呉に降伏し、曹操の天下統一で三国時代ではなく「魏」と歴史には記載されていたのではないかと、思います。少なくとも、神奈川のYさんも書かれていたように、孔明と周瑜(とくに孔明)は本人が優れていたからか人を見る目があるとかいえず(劉備や孫権はさすが主君で、見る目があった)、一方魯粛は人の本質を見抜く目があったのでしょうね(これは、魏の司馬懿にもいえること)。