皆さま、鈴木貫太郎氏をご存知でしょうか?
好きな言葉は”正直に腹を立てずに撓まず励め”で、お写真だと一見好々爺風のおじいさん、リメイク版の「日本のいちばん長い日」では冒頭では、耳が遠く、昭和天皇に耳打ちされるおじいちゃん総理大臣のイメージがあります。
彼は昭和天皇の侍従長していたとあり、穏やかな雰囲気がありますが、彼は日清、日露戦争で艦隊で戦い、水軍の最高位まで叩き上げて昇りつめた武人で、2.26事件で襲撃されるも、復活し、疲弊した日本を昭和天皇と阿南惟幾氏ともに終戦に繋げた政治家の一人です。
その手腕は柔らかな立ち回りで暴走していた陸軍の剛を、阿南惟幾氏と制するやり方で(*まさに、柔よく剛を制すby基礎医)、昭和天皇の意を良く測り、良く汲み、最終的に日本の未来に繋げる成果を残し、この姿勢は昨今の皇位継承、皇統問題で、陛下や民の意を汲まない議員達に習ってほしいと感じた次第です。
鈴木貫太郎氏は、
1868年1月18日に和泉国生まれました。(現在の大阪府堺市中区)父が下級官吏の苦労人だったとあり、引っ越しが多く、1871年に本籍地である千葉県東葛飾郡関宿町(現・野田市)に居を移し、また群馬県に引っ越します。
子供の頃の鈴木貫太郎氏ですが、
好奇心強く、馬に近づいたところ蹴られて死にかけたり、川で溺れて死にかけたなどの逸話を持つ、何かと波乱万丈で生きて行きます。
そんな中、
1884年に海軍兵学校に入校し、1895年には日清戦争に従軍します。この時、海軍では薩摩生まれじゃないと出世が難しいと言われ、鈴木貫太郎は色々言われながらも頑張ります。威海衛の戦いに参加しますが、発射管の不備もあって夜襲では魚雷の発射に失敗したものの、湾内の防材の破壊や偵察などに従事したとあります。その後、海門航海長として台湾平定に参加、次いで比叡、金剛を経て、1897年に海軍大学校入校、砲術を学び大成して行きます。
同年に結婚し、1903年の9月26日に、鈴木貫太郎氏は中佐に昇進しましたが、一期下の者たちより低いその席次に腹をたて、退役まで検討していた中、父から「日露関係が緊迫してきた、今こそ国家のためにご奉公せよ」という手紙を受けたことにより、思いとどまり、海軍人生を歩みます。この頃、対ロシア戦のため、日本海軍は軍備増強にて、アルゼンチンの発注でイタリアにおいて建造され竣工間近であった装甲巡洋艦「リバタビア」を急遽購入して巡洋艦「春日」を持ち、鈴木貫太郎氏はその回航委員長に任じられました。
1904年、2月に日露戦争が始まり、
鈴木貫太郎氏は「春日」の回航委員長として、僚艦「日進」と共に日本に向け回航中で、日本に到着すると鈴木はそのまま「春日」の副長に任命され、黄海海戦にも参加します。その後第五駆逐隊司令を経て、翌1905年1月に第四駆逐隊司令に転じます。(エピソード、ウィキペディア参照。)ここから鈴木貫太郎氏の海軍大将の本領発揮で、持論だった魚雷等の高速近距離射法を実現するために猛訓練を行い、そのスパルタから、部下から鬼の貫太郎、鬼の艇長、鬼貫と呼ばれたそうです。第四駆逐隊司令として鈴木貫太郎氏は日本海海戦に参加し、ゴツい敵旗艦である戦艦「クニャージ・スヴォーロフ」、同「ナヴァリン」、同「シソイ・ヴェリキィー」に魚雷を叩きこみ、命中させるなどの戦果を挙げて勝利に貢献します。
日露戦争後には、海軍大学校の教官になり、駆逐艦、水雷艇射法について誤差猶予論、また軍艦射法について射界論を説き、海軍水雷術の発展に理論的にも貢献して、この武勲により、功三級金鵄勲章を受章したとあります。
そんな中、あるきっかけで昭和天皇とのご縁が始まります。
今回はここまで。
(鈴木貫太郎氏その2)に続きます。
文責 神奈川県 神奈川のY

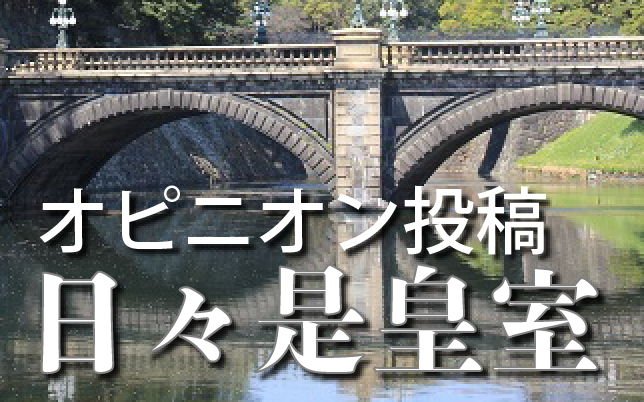
1 件のコメント
あしたのジョージ
2025年5月10日
鈴木貫太郎氏の事は何にも知らないので勉強になります。
昭和天皇のとの御縁があった話、楽しみですね。