
今回のテキストは『「いき」の構造・他二篇』(九鬼周造著)から「風流についての一考察」です。風流を構成する要素は離俗(世俗的価値の破壊)と耽美(芸術的価値の建設)と自然(自然美への回帰)であり、風流にあっては自然美(離俗&自然)と人生美(耽美&自然)は共存でき、また絶対的であると共に個性や時代によって相対化される存在でもあるそうです。それゆえ風流には不易と流行の二重性があり、例えば千家流や談林風といった型も時代と共に更新されねばならず、つまり変えてよいルール(規則)と変えてはならないエートス(慣習)があるわけです。型だけで残った伝統(因習)が当事者や周囲の人々を苦しめる場合も数多あるからです。ちなみに世界的な映画監督・小津安二郎は「何でもないことは流行に従い、大事なことは道徳に従い、芸術のことは自分に従う」と言いましたが、古の風流人も九鬼も小津も因習を排除して伝統を残してきたからこそ、現代まで伝わったり世界的に評価されたりしたのだと言えます。
さて、風流が体現する美的価値には「華やか」と「寂び」、「可笑しみ」と「厳か」、「細い」と「太い」という3つの対立軸があり、これらを頂点とする正八面体を描くことができます。風流の対立軸では歴史的に寂・笑・細が優勢とされてきたと言えます。例えば九鬼は、「寂」←→「華」の対角線と「細」の頂点で構成される直角三角形が「もののあはれ」とし、その寂側の半分が「侘び」としていますが、変化する事物に触れた際の感動を意味する「もののあはれ」は、現代の解釈では「侘び」「寂び」側に寄り過ぎだと感じられます。こうして季節の消退(秋冬)にのみ注目し
て隆盛(春夏)を無視すれば「花の下にて春死なむ」(西行)という感覚は失われ、死は忌むべきもの(儒教)となり、コロナ自粛禍で顕在化したような生命至上主義(キリスト教?)にも至るでしょう。
「べらぼう」劇中での平賀源内(安田顕)は自由人として描かれましたが、彼が風来山人名義で著した『風流志道軒伝』では、「唐の反古に縛られて我が身が我が自由にならぬ屁っぴり儒者」として先例主義者を批判しています。世俗(作家・芸術家)と自然(本草学者・山師)を行き来した自由人&風流人の源内は男娼街に通う生粋の男色家でもありました。やはり本来の日本文化は儒教ともキリスト教とも相性が悪いのでしょう。
文責:京都のS

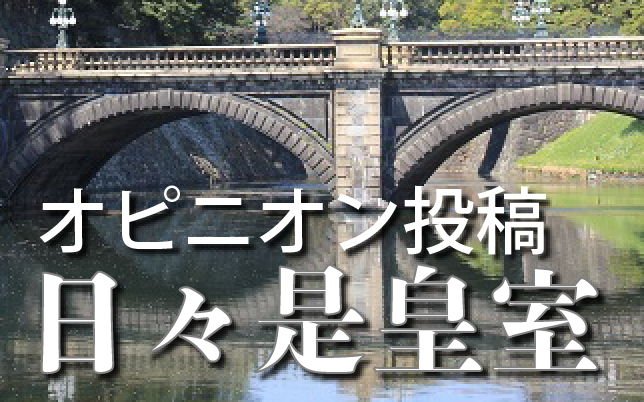
1 件のコメント
京都のS
2025年5月25日
掲載、ありがとうございました。『「いき」の構造・他二篇』からは2回目です。1回目は「野暮天としての男系固執派は己のカッコ悪さに気付こう!」( https://aiko-sama.com/archives/55150 )です。他1篇は使いにくいので前掲書からは最後です。