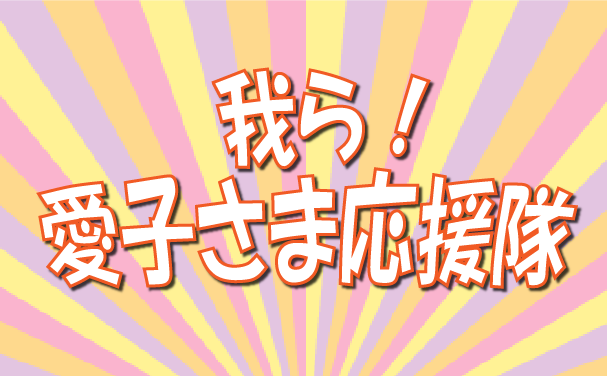7/9放送の「知恵泉」を紹介しました。
こちらの感想を希蝶さんがくださいましたのでご紹介します!
以下本文
「知恵泉」、視聴しました…。なかなかの内容だった、と思います。
奈良時代の女官を代表する存在として、飯高諸高(いいたか の もろたか)(笠目〔かさめ〕)と、和気広虫(わけ の ひろむし)が取り上げられていました。妥当な人選なのかな?
前者は…歴史マニアでないと、ご存じない人もいたのでは、と思います。某人気(?)女医ドラマと、昨今復活したNHKのドキュメンタリーとのリンクは…ちょっとでしたが。
後者は和気清麻呂の姉で、法均尼(ほうきんに)とも呼ばれており、宇佐八幡宮神託事件でも有名なので、ご存じのかたもいたのでは、と思います。何気に、某「残酷」女流漫画家が一瞬登場もしていましたが…。
れいにゃんさんがインタヴューでも語られていましたが、こういうかたがたは、自身が(史実にもとづく)フィクションとしてとり扱った題材をどのように感じているのか、伺ってみたいような気がします。
よく男系派は宇佐八幡信託事件を引き合いに出して、天皇陛下の裁定に過失・瑕疵があったら、正すべきだ、天皇が日本の伝統を壊すつもりなら、いさめるべきだと主張するようですが、この場合は称徳天皇から道鏡への天皇位の、いわば中国風の「禅譲」に無理があるだけで、改めるべきところを更新してゆくという「伝統」の考えとはそぐわない、(東西双方の意味での)「革命」思想だった点にあるのでは、と思います。番組中では、宇佐八幡宮の神官が、社を格上げをするために道鏡を利用しようとしただけではないか、とも述べられていましたが。
私がよんだ、奈良時代の女官の著書を記された女性学者さんも解説をされていて、なかなか興味深い番組でした…。
この二人はそれぞれ『続日本紀』『日本後紀』に薨伝が載っています。講談社現代新書に現代語訳もあるので、興味のあるかたは…よんでみても面白いかも。
ちなみに(番組中でも述べられていたように)奈良時代は低い身分の女官が出世することが頻繁に行われていて(諸高はその典型的な例)、ほかにも尾張小倉(おわり の おくら)、熊野広浜(くまの の ひろはま)、壬生小家主女(みぶ の おやかぬしめ)などが有名です。最初と最後の人は、それぞれ「尾張国造」・「筑波国造」の称号を朝廷から与えられています。
再放送、されるのですよね?そうでなかったら、NHK+などで、是非とも。
希蝶さんどうもありがとうございました!
当サイトでは、知恵泉の感想他、皆さまのご意見を募集しています(^^)
是非ぜひお気軽に!