
不干斎ハビヤンという室町末期から江戸初期に生きた日本人を御存じでしょうか?『日本教徒』(山本七平著)によれば、ハビヤンは信仰の面では禅僧からキリスト者を経て儒者となりましたが、彼が一貫して日本教徒だったからこその変遷だったそうです(※ハビヤンはキリスト教の洗礼名)。彼には幾つかの著書があり、キリスト者時代に著した『ハビヤン版・平家物語』はパードレ(神父)のために書かれた日本語と日本学の教科書ですが、これは見事な日本人論だったようです。
『平家物語』において平家一門や木曽義仲が敗れた理由は「人をも人と思わず」「世を世とも思わぬ」からだと言い、さらに「受恩の義務」(受けた恩を返す義務)を果たさず、「施恩の権利」(施した恩を返してもらう権利)を主張したからだと言います。この場合の恩とは親や目上から受けた恩を指します。
ここで連想されるのは『「世間」とは何か?』(安部謹也著)における世間の掟「長幼の序」と「互酬制」です。また「日本教=人間教=世間教」という公式を想定すると、人や世間を蔑ろにする忘恩の徒は人々から反感を買って敗れ去るとも言えます。しかし、この考え方は「勝てば官軍、負ければ賊軍」に繋がり、敗北には相応の理由があったとの理屈が付き、さらに「イジメはイジメられる側にも原因がある」や「他人様や世間様に迷惑を掛けるな」といった「世間の暗部」とも直結します。そして著名人や皇室関係者のスキャンダルは世間様に迷惑を掛けたとの下らな過ぎる理由で断罪されることになります(後に嫌疑が間違いと判明しても!)。
一方、「受恩の義務」を一心に果たそうとして敗れた者に対して働くのが「判官びいき」です。後白河法皇に尽くした源義経も後醍醐天皇に尽くした楠木正成も、命懸けで「受恩の義務」を果たそうとしたから最も日本人が好む悲劇の英雄です。しかし、それなら歴代天皇への「受恩の義務」を果たすべく命を散らした日本兵に対し、戦後日本人は何故「判官びいき」が働かないのでしょうか?戦後日本人の意識では昭和天皇よりマッカーサーが偉く、「勝った米軍は官軍」「戦勝国様に迷惑を掛けた」がデフォルト化したからでしょうか?
さて、日本国民は皇室から受けてきた歴史的な恩(内戦回避etc.)を返すべきだと私は考えます。ゆえに令和の皇族方が愛子天皇誕生やジェンダー平等を望んでおられると拝察されたら、それらを叶えて差し上げるのが真っ当な日本教徒(日本国民)だとも考えます。
文責:京都のS

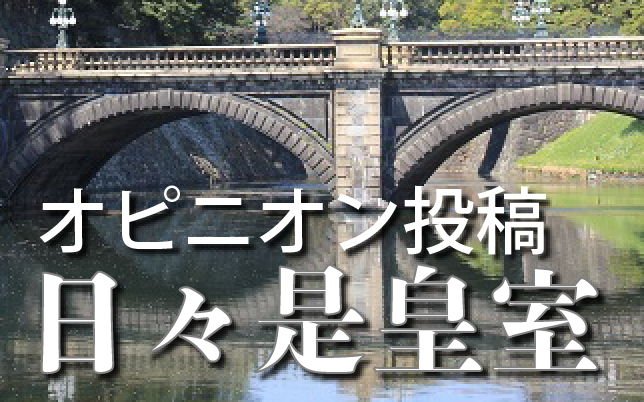
1 件のコメント
京都のS
2024年8月20日
掲載ありがとうございました。いつもは「光る君へ」(※『源氏物語』を書いた作者の一代記)のプチ連載(最新回: https://aiko-sama.com/archives/42853 )ですが、今回は『平家物語』です(笑)。