3月10日午後1時より行なわれた、3回目の「全体会議」終了の直後、立憲民主党と日本維新の会が、いち早く記者会見の動画を公開しました。ここでは、日本維新の会 の 会見の文字起こしをしたので、立憲民主党 の 会見に照らし合わせながら読んでみます。
以下、藤田文武議員(44歳)の文字起こしです。青枠は立憲民主党の会見から参照、緑枠は担当者より割込み。
*前回の、有識者会議の①案:女性皇族の婚姻後皇籍を離脱しない案に続きまして、今日は第②案である男系男子を養子縁組で迎える案についての議論が、論点を絞って行われました。
いくつか論点がありましたが、それぞれの態度表明各党からあり、馬淵議員から、いくつか論点に対して議論を集中的にしたい、という論点整理があった後に、それについての意見交換もありました。
- 立法事実の欠如
- 先例との整合性
- 憲法の適合性、疑義
- 事実上の不都合
まずは、立法事実のところで、不確実性の観点から誰が対象でどういう風に今把握されているか、等の質問と投げかけもありました。
(馬淵議員) 1つ目の立法事実の欠如に関しては、そもそも11宮家の男系男子の子孫という方が、該当者がいらっしゃるのか、その意思は如何なるものなのか。これについては政府は、質問趣意書の答弁を見ましても、「確認していない」という答弁を出されています。内閣委員会での質疑でも、官房長官からも同様の答弁をいただいてますので、確認ができていないという状況であるということ。すなわち立法事実が分からない。
内閣委員会における松野官房長官の答弁
馬淵先生にお答えをいたします。有識者会議の報告書においては、皇族数を確保する方策の一つとして、養子縁組により皇統に属する男系の男子を皇族とする方策を制度論としてお示しをしたところでありますけれども、昭和22年10月に皇族の身分を離れたいわゆる旧11宮家の子孫の方々について、政府として具体的に把握したり、接触を行っているものではありません。
それから、今言われている11宮家ですね。昭和22年に皇籍を離脱された11宮家の…という風に、今、対象が注目されてるわけでありますけれども、それの妥当性等の論点がありました。
それから1つ指摘でありましたのが、先例というものが、前回も、我々も主張してるとこでありますけれども
それで考えた場合に皇籍を離脱された方が養子という手段でお戻りになった例は先例にはないんだ、というご主張がありました。その件についてはちょっと議論色々あって、私もその点述べさせていただきました。
まず、そもそもこの養子案というのは、法制局または内閣参与からのご説明もあったんですけれども、例えば日本でも民間でも古いお家または伝統的な生業をされているお家等が、親族から養子を取るという例は結構ありましてですね、そういう国民的な習慣みたいなものから、受け入れられやすいんじゃないかという、そういう配慮等からも妥当性があるんじゃないか?という議論が過去にありました、というご紹介がありました。
で、その上で、養子縁組というのは今は法律上禁止されてるわけでありますけれども、皇族は。その先例は過去にはある、ということ。それから皇籍を離脱された方が、そのまま皇族にお戻りになるという事例はある、ということがありました。
私がちょっと…その指摘を何度もおっしゃるんで…主張として申し上げたのは、先例も、やっぱり考えないといけないのは、まず原則と、その原則を達成するというか、お守りするための手段や手法については、分けなければならないというのがありまして。
2.先例との整合性
“原理” “原則”という言葉も織り交ぜながら、先例についての藤田議員の主張が続きます。一旦、馬淵議員の会見の発言と比べてみましょう。
(馬淵議員)2つ目に先例の整合性です。これについても申し上げたところです。過去において、これも様々、事実関係を確認しましたところ、過去において、臣籍降下、すなわち昔の時代でありますから、国民と称するか別としましても少なくとも、国民という状態の中で養子によって皇族となった方というのは存在いたしません。過去あったものといえば臣籍降下、すなわち皇族であった方が皇族でなくなった場合に、その方々が何らかの理由で、また再び皇族に戻るというのがありましたけれども、あくまでもこれは皇族であった方が皇族に戻るのであり、一般国民である方が養子になった例ではございません。
このように、過去の事例から見ても、先例にないことをするべきではないというご意見を前回、複数の党会派から頂いたんですが、この養子案というものが、そもそも先例にないものであるということを申し上げました。
加えて申せば、先例というのは、その時代時代に合わせて変わってきています。これも旧憲法下におきましては、一般国民とされた女性が、結婚された場合、婚姻後は皇族になるという、これも過去になかった例ですし、また側室という制度も、これは現時点においてはなくなりました。
つまり時代に合わせて、このように先例というものというのは、どんどんと制度が変わっていくんだということで、それこそがまさに開かれた、これからあるべき皇室の姿ではないかということを申し上げたところであります。
前回(第二回全体会議)も、例えば現行法上では、例えば側室制度というのは、そもそも先例にあったけども、今ないから先例と違うんじゃないか!であるとか、または、女性の方が男系であっても女性の方が天皇陛下になられる、即位されるという例はあったけれども、現行法では男系男子と規定されているじゃないかと。だから先例は時代によって変わっていくべきものなんだ!と、そういうご主張がありました。
私が申し上げたのはですね、例えば1つの視点は、先例があって、その先例は所謂男系なわけでありますけれども、男系男子はその先例範囲内で、少し選択肢を狭めていると。先例を広げるんじゃなくて狭めているところでありますし、それから側室制度も同じように手段を狭めている、という話であります。
ですから、男系という原則を変えるというのはこれはもう次元の違う話でありまして、その手段については、まあ、それを狭めたりまたはアレンジするということは、時代によって、あって然るべきだという意見を、私からは申し上げました。
その上で、過去に先例がある、
皇籍を離脱された方が復帰する、という先例。
それから養子縁組という先例。
この2つはあってですね。
この組み合わせがないという風におっしゃられますが、私はむしろこれは補強する案でありますし、むしろ妥当性が高いという風に申し上げました。
それから11宮家に絞るのか議論も、少し、色々、出ましてですね。
ここについては1つの過去の議論または有識者会議等の意見等を鑑みるとですね、
まずこの昭和22年に皇籍を離脱されたのが11宮家26名されたわけでありますが、全て伏見宮の系統に属する方々でありますけれども、
これは現行憲法下、または皇室典範の元においても短期間でありますが、皇籍を持っておられたという、そういう方々であります。そういった意味でどこかで線引きをする!ということであるならば、1つの大変重要な要素になり得ると。そういう考えでありまして、そうしたご説明も政府からもございました。
〈記事紹介・感想〉第19弾 森暢平成城大教授の警鐘(これでいいのか「旧宮家養子案」) 皇籍離脱を自ら申し出た旧皇族について、過去の議論で意見が出されたけれど検討はしていない、と。
(馬淵議員) 旧11宮家男系男子以外の皇統に属する方と考えられる方、そこに広げるのかということについても、有識者会議報告書の中には検討した形跡がない、ということです。
あとは対象者がいるのか、またその意思をどう確認するか
みたいなことが指摘でありましたが、これは非常に難しい問題でして、現行法制下で養子縁組みできないわけでありますから、いわゆるそれをやるということは、現行法制においては違法という形になるわけでありまして、それの仮定を置いた上で個別名を上げてですね、やるということにおきましては現代のこの「個人のプライバシー」という観点もありましてですね、非常によろしくないし、抑制的にやるべきだという、そういうお考えが衆議院法制局だったかな?とかからもご示唆がございまして、制度化してからでないと、具体名を上げてはやりにくい。それは私も当然のことだという風に思いました。
(野田佳彦代表がかみ砕いて言っています。)
ザクっと言うと、立法事実の確認ができないというのは、今、例えば養子縁組というのは皇室典範で認められてないことじゃないですか。だから違法なことを「あの、あなたその意思ありますか?」という確認することはできないみたいな説明をしていました。
野田代表は、自民党の他に複数の会派の発言としていますが、藤田議員は、衆議院法制局が養子案の違法性を認めていたと認識しているようです。
そういった議論が様々ございまして
その他で言いますと、この悠仁親王殿下までの流れをゆるがせにしないということを、しっかりと確定させて、それを先に表明すべきじゃないか、という、そういうご指摘もありました。それについては玄葉副議長から、その前提でこの議論は進めている、という、そういう趣旨のご発言がありました。
私からはそんなとこかな。あとはそれぞれ色々お立場から議論がありました。
今日の全体の感想いきますと、この男系男子の養子縁組案については、主要政党はほとんど賛成の立場でありますが、立憲民主党それから馬淵議員から、割とこの論点を深掘りする、そういうご示唆もありましたんで、ここをしっかりと整理して、制度設計の段階に入っていくと、
そういうのが望ましいんじゃないかと私も参加して感じたところでございます。私からは以上です。
前回(第二回全体会議)の冒頭、玄葉副議長の発言がありました。本 日 の 議 論 と い う の は 、 政 府 報 告 に 示 さ れ た 皇 族 数 の 確 保 の 方 策 に つ い て の 議 論 と し て ば か り で は な く て 、 国 会 と し て 示 し た 附 帯 決 議 、 す な わ ち 安 定 的 な 皇 位 継 承 確 保 策 を 議 論 を す る と い う 、 そ う い う 附 帯 決 議 が ご ざ い ま す け れ ど も 、 そ の 附 帯 決 議 が 土 台 に あ る ん だ と い う 認 識 を し て お り ま す。
(馬淵議員) 最後に副議長にも申し上げましたが、こうした問題点について十分な議論がなされないまま、大枠の制度を早く作れという声もありましたので、それは拙速に過ぎないのかと。
やはり国民に開かれた議論を重ねていくということにおいて、まだまだ十分ではないということを申し上げて、会は終了したというところであります。
もし深掘りのご質問あったらお願いします。
前回、2月3月で複数回期間を置かずにやっていくというお話があったので、今までのペースで言うと再来週ぐらいにはあるんじゃないかなという風には予想はしています。
議論については、前回の議事録上がってるのかな?また皆さん見てください。よろしくお願いします。
文字起こしは以上です。
第二回全体会議の議事録あがっています。進んでいます。
藤田文武議員(44歳)のご希望通り、じっくりまっすぐ、皆で読みこんで参りましょう。
「愛子天皇への道」サイト運営メンバー れいにゃん

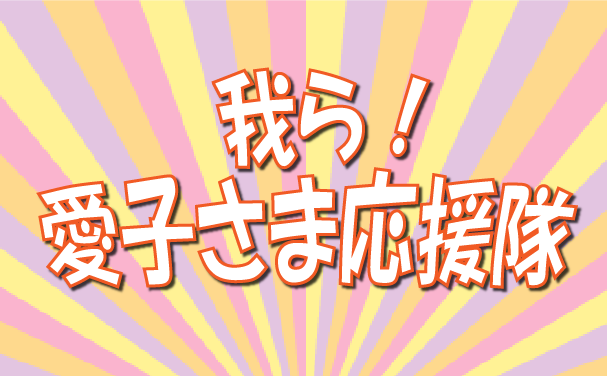
3 件のコメント
SSKA
2025年3月14日
単純に旧宮家系養子案は制度化以降のプランニングが誰一人出来ていないのに、何の目処も無い誓いの言葉を法制化しようと自白しているだけです。
立法者として通常の法律を立てる際にこんないい加減な立て付けで国会に持ち込む等あり得ない事くらい分かっているくせに、ペテンにも程があります。
こん
2025年3月14日
旧宮家案をぶっ潰せば、いよいよ【ゆるがせ】を、ぶち壊す時ですね。ゆるがせについても何は法的根拠はありません。
『内閣に設置された有識者会議が“宿題”から逃げ出す為に持ち出した、底の浅い口実に過ぎない』
と高森先生も仰っていますので、いよいよ本丸への攻撃を開始する時が来たのだと思います。
突撃一番
2025年3月14日
例えばの話、大麻合法化に賛成する人に、「もし将来合法化されたら、アナタは大麻を吸いたいですか?」とアンケート取る事は、何らおかしな事ではないですよね?
そもそも共同通信とか毎日新聞が行った、皇位継承に関する世論調査だって、現行皇室典範では明らかに「違法」である女性天皇の是非について問うものなんだから、それもダメという事になってしまう。
「現在違法だから、意思確認は取れません」ってのは、完全に詭弁です!!
むしろ、養子制度が実現してから意向調査に踏み切って、もし対象者全員から拒否されたら、制度実現の為に費やした審議時間・労力・費用の全てが無駄になってしまうぞ。
ただ「君臣の分義を破壊する制度」を、後世に残しただけで終わっちまう。