読売提言を受けて、産経新聞がさらに記事を出しています。
「女系天皇」読売は昨年から主張していた 渡辺恒雄氏の「遺言」と考えるとつじつまが合う【産経新聞】
渡辺恒雄氏の「遺言」であったかどうかは、定かではありませんが、読売新聞が昨年から安定的皇位継承に関する社説を出していたのは確かなことです。
与野党協議の初会合では、皇族女子が結婚後も身分を保持することで 概 ね一致した。一方、皇族女子の配偶者とその子を皇族とするかどうかでは見解が分かれた。
自民党は、配偶者と子は皇族としないことが適切だと主張した。将来、皇族女子の子が皇位を継ぐことになれば女系天皇となり、男系で126代継承してきた皇室の伝統を覆すことになるからだ。
ただ、配偶者と子を一般国民とした場合、政治活動や自らの意見表明が自由にできることになる。皇室の政治的中立性や品位を保てるのだろうか。
昨年、2024年5月17日に行われた与野党協議(全体会議)の初会合を受けての読売新聞の社説。この時点から、読売新聞は、2025年5月15日の提言に挙げた「夫・子を皇族に」を示唆していたことが分かります。
ただし、この昨年の社説は、「将来、皇族女子の子が皇位を継ぐことになれば女系天皇となり、男系で126代継承してきた皇室の伝統を覆すことになるからだ。」という一文の主体が自民党なのか読売新聞なのかかが曖昧で、2024年11月5日に報じられた国連の女性差別撤廃委員会から皇室典範へ勧告に対する社説は、さらに物議を醸すことになりました。
社説 皇室典範に勧告 歴史や伝統を無視した発信だ【読売新聞】
日本の皇室制度は長い歴史の中で培われてきた。男系男子による皇位継承は、今上天皇を含めて126代にわたる。また、一時的に女性が天皇になった例もある。
2024年11月の社説を鑑みれば、2024年5月の一文の主体は、読売新聞であり、男系男子固執の保守層にも配慮したものであったと言えると思います。
しかしながら、2025年5月15日の四つの提言と共に報じられた社説には、男系男子固執から脱却する文言が並んでいました。
皇室の存続には、安定的な皇位継承が欠かせない。
現行の皇室典範は、父方が天皇につながる「男系男子」に皇位継承権を限定している。現在、皇位継承の資格を持つのは、秋篠宮さま(59)と長男の悠仁さま(18)、上皇さまの弟の常陸宮さま(89)の3人に限られている。
現行制度を前提とすると、悠仁さまが結婚して仮に男子が生まれなかった場合、皇位の継承者がいなくなってしまう。
◆配偶者や子も皇族に
男系男子にこだわり続ければ、象徴天皇制の存続は危うくなる。女性天皇や、女系天皇の可能性を排除すべきではないだろう。
歴史上、女性天皇は8人存在した。また、憲法は皇位について「世襲」と定めているだけで、政府も女性・女系天皇を「憲法上は可能」と解釈している。
安定的皇位継承に真に資する「女性天皇・女性天皇」への突破口となる「夫・子も皇族に(女性皇族の配偶者の方とお子様を皇族に)」を提言とした読売新聞が、5月15日に紙面で第一面、第三面、第十四面、第十五面で展開した夥しい記事の数々は、国民の総意である
「愛子さま立太子」実現を国会議員に促すものでした。
読売新聞は、9割の国民が支持する方向に、完全に舵を切ったのです。
かつては「女性天皇 前向きな論議を期待する」と主張していた産経新聞。もしかすると変るときを探りながら、読売提言に関する記事を連打しているのではありませんか?
「愛子天皇への道」サイト運営メンバー まいこ

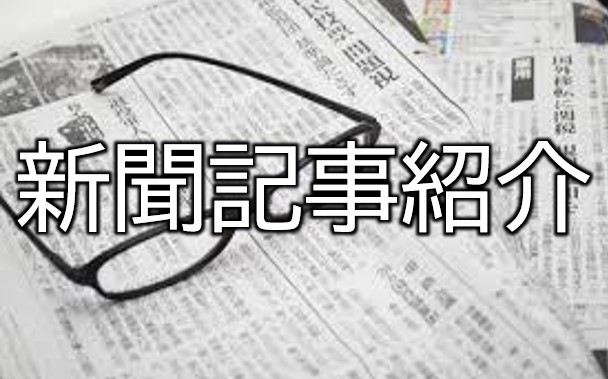
2 件のコメント
ダダ
2025年5月18日
読売新聞の記者は、少なくともこの1年間は取材を重ねて皇統問題を真剣に学んだことが分かります。
そこに発行部数トップという慢心はなく、読者に読んでもらうための努力があります。
論理の力・優劣は、多数決(発行部数)では決まりませんが、お仲間と戯れているだけの産経新聞がそれに気づくことは無いでしょう。
SSKA
2025年5月18日
渡辺恒雄にアンチが多いのを利用し分断する真似をして本当にどうしようもないですね。
読売が左傾化、朝日化したと言うのは全く間違いでしょう。
安倍晋三とお仲間が違憲違法な手段によって政策を作り長期政権を維持して来た問題について、彼の死後その多くが露見し社会全体が戻ろうとしている流れが、違法献金、統一協会に続き皇室問題で最大ピークに達しつつあると見るべきだと思います。
(自称)保守が違法性の下で運営して行く馬鹿な考えに一定の歯止めが掛けられるタイミングなのでしょう。
男系主義なんぞは結局死人の言葉で現実に生きている人間を縛るのと同じ事で、幽霊船に無理矢理乗せて黄泉の国に連れて行く死神や死霊の様なものだと頭を冷やして見たらと思います。
イタコが亡くなった○○を降霊してこう言っていると訴える宗教を新聞で広める馬鹿さ加減に何時になったら気付くのでしょうね。