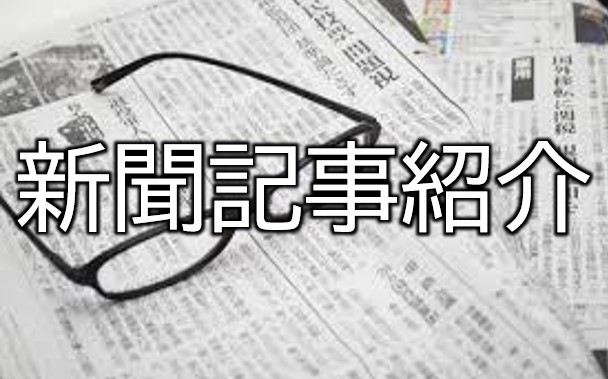読売提言を受けて、産経新聞が社説を出しました。
社説<皇統と読売提言>分断招く「女系継承」は禁じ手だ 論説委員長 榊原智【産経新聞】
初代神武天皇から第126代の今上(きんじょう)天皇まで継承の経緯が全て伝わっており、皇位継承の最重要原則は男系(父系)継承だと分かる。
(中略)
天皇は祭祀(さいし)王でもある。語義矛盾の「女系天皇」「女系皇族」では、日本の神々や皇室の祖先に国民の繁栄を祈ることはかなわない。それでよいわけがない。
要するに、女性は男の王ではないので、祭祀は出来ないというのが産経新聞の見解。
この文言、全体会議における「(養子案を)憲法自体が許容している」という内閣法制局の説明に通うものがあります。
○ 内 閣 法 制 局 第 一 部 長 ( 佐 藤 則 夫 君 ) 内 閣 法 制 局 で ご ざ い ま す 。 ま ず 、 憲 法 十 四 条 と の 関 係 に つ き ま し て 申 し 上 げ ま す と 、 憲 法 二 条 、 皇 位 は 世 襲 の も の で あ る 、 こ れ は 、 法 の 下 の 平 等 を 定 め た 憲 法 十 四 条 第 一 項 の い わ ば 特 則 を 成 す 規 定 と 解 さ れ る と こ ろ で ご ざ い ま す 。
こ の よ う な 特 則 で あ る と い う こ と を 踏 ま え て 、 皇 族 の 範 囲 に つ き ま し て 、 あ る い は 皇 位 の 継 承 の 順 位 に つ き ま し て は 、 皇 室 典 範 と い う 法 律 に 委 ね ら れ て い る と 解 さ れ ま す 。
そ の 上 で 、 養 子 縁 組 と い う こ と に つ き ま し て 申 し 上 げ ま す と 、 こ の よ う に 、 第 二 条 に お き ま し て 皇 位 は 世 襲 の も の と し 、 ま た 、 憲 法 第 五 条 及 び 第 四 条 第 二 項 に お き ま し て 摂 政 あ る い は 国 事 行 為 の 委 任 の 制 度 を 設 け て お り ま す こ と か ら 、 こ れ ら の 制 度 を 円 滑 に 運 用 す る こ と は 、 こ れ は 憲 法 自 体 が 要 請 す る と こ ろ で あ り 、 こ の た め 、 皇 統 に 属 す る 方 を 新 た に 皇 族 と す る こ と も 憲 法 自 体 が 許 容 し て い る の で は な い か と 考 え ら れ ま す 。
内閣法制局の見解は、摂 政 あ る い は 国 事 行 為 の 委 任 の 制 度は、男系男子しかできないので、養子案は違憲ではないということになると思います。
これに関連して、内閣官房参与・山崎氏は、さらに説明を試みていました。
○ 内 閣 官 房 参 与 ・ 皇 室 制 度 連 絡 調 整 総 括 官 ( 山 﨑 重 孝 君 )
ま ず 、 皇 統 男 系 男 子 に 限 っ て 養 子 に す る と い う 入 口 の 部 分 が い か が か と い う お 話 が ご ざ い ま し た 。
こ の 話 は 、 元 々 の 発 端 が 、 悠 仁 親 王 殿 下 が 御 即 位 な さ っ た と き に 皇 族 が 一 人 も い ら っ し ゃ ら な く な る よ う な 事 態 を ど う す る か と い う こ と か ら 始 ま っ て お り ま し て 、 そ の と き に 、 実 は 、 現 皇 室 典 範 で す と 摂 政 だ と か 、 あ る い は 、 こ れ は 臨 時 代 行 の 法 律 で ご ざ い ま す が 、 天 皇 陛 下 が 国 外 に 行 か れ た と き に 代 行 す る と い う 方 々 は 、 基 本 は 皇 室 内 の 男 系 男 子 の 方 に な っ て お り ま し て 、 男 系 女 子 の 方 も ご ざ い ま す が 、 男 系 の 方 々 に な っ て お り ま し て 、 妃 殿 下 方 は 、 基 本 は 、 皇 后 様 、 皇 太 后 様 、 太 皇 太 后 様 以 外 は 摂 政 に は な ら な い ふ う に な っ て お る わ け で ご ざ い ま す 。
そ う い う こ と を 考 え ま す と 、 い ろ い ろ な 公 務 全 て の こ と を 支 え て い た だ く よ う な 皇 族 の 方 と い う こ と に な る と 、 男 系 男 子 と い う と こ ろ を 入 口 に す る こ と が よ ろ し い の で は な い か と い う 議 論 に な っ た と こ ろ で ご ざ い ま す 。
皇室典範
第十六条 天皇が成年に達しないときは、摂政を置く。天皇が、精神若しくは身体の重患又は重大な事故により、国事に関する行為をみずからすることができないときは、皇室会議の議により、摂政を置く。
第十七条 摂政は、左の順序により、成年に達した皇族が、これに就任する。
一 皇太子又は皇太孫
二 親王及び王
三 皇后
四 皇太后
五 太皇太后
六 内親王及び女王
前項第二号の場合においては、皇位継承の順序に従い、同項第六号の場合においては、皇位継承の順序に準ずる。
→皇 后 様 、 皇 太 后 様 、 太 皇 太 后 様が摂政になれるということならば、現皇室典範においても、女性が摂政に就任するということ。
しかも皇室典範の第十七条をよくみれば、「六 内親王及び女王」とありますので、内親王である愛子さま、佳子さま、女王(じょおう)である彬子(あきこ)さま、瑶子(ようこ)さま、承子(つぐこ)さまと、摂政に就任する方はいらっしゃいます。天 皇 陛 下 が 国 外 に 行 か れ た と き に 代 行 す ることにも、何の問題もありません。
卑弥呼は祭祀王と呼ばれており、祭祀を女性が行うことそのものが日本の伝統ともいえますね。
「愛子天皇への道」サイト運営メンバー まいこ