
「光る君へ」の主人公まひろ(後の紫式部:吉高由里子)は幼少期(落井美結子)から酷い目にばかり遭っています。世渡り下手な父・藤原為時(岸谷五朗)が官職に就けなかったために生活は貧しく、実母ちやは(国仲涼子)は当時の最高権力者・藤原兼家(段田安則)の次男・道兼(玉置玲央)に殺され、上級貴族たち(公任・斉信…)が打毬に興じていた現場で「女こそ家柄」「まひろ?あれは無い」と噂され、仲良くなった散楽(権力を揶揄する演目が多かった)の一員・直秀(毎熊克哉)は騙し討ちみたいに検非違使に惨殺され、文字を教えていた少女たね(竹澤咲子)は政の不作為で蔓延した疫病で死に、三郎(木村皐誠)と呼ばれていた頃から恋い慕っていた藤原道長(柄本佑)は家柄の良い源倫子(黒木華)に婿入りし…。
普通これだけの目に遭ってきたら凄まじいルサンチマン(怨念)に囚われて反権力の闘士やヒステリックフェミニストになっても可笑しくないのですが、”まひろ”は後宮に入内した彰子(藤原道長と源倫子の娘:見上愛)に女房として仕え、皇后・定子(高畑充希)が崩御した後も忘れられない一条帝(塩野瑛久)の目を中宮・彰子に向けさせるべく、彰子に一流の教育を施し、かつ帝の気を引けるぐらい面白い『源氏物語』の執筆も続けました。
つまり、これは紫式部の与党精神だと言えます。道長から請われた面も多分に有りましょうが、外野で騒いでいても政が良くなることは無いので体制側に入り込んで政を内から変える道を選んだわけです。
”まひろ”の友”ききょう”(清少納言:ファッサマ)は劇中で「自分のために生きることが他の誰かのためにもなっている、そういう生き方をしたい」と言いましたが、結局”ききょう”は定子のためだけに『枕草紙』を書き、民のために政を変える方向には意識が向かず、一条帝が定子にのめり込んだ(私に走った)時も定子(と一条帝)を全肯定していました。定子・一条帝・伊周(三浦翔平)らとの御仲間主義(私&集)に堕した清少納言と公のために権力者・道長とも戦えるよう彰子の個を鍛え上げた紫式部との違いはココ(与党精神&公共心)だと思われます。 (文責:京都のS)

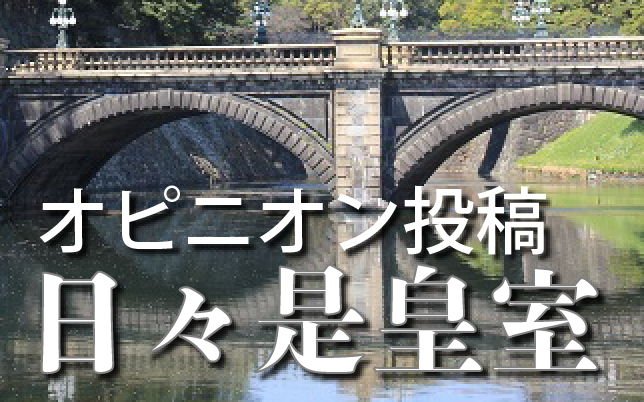
2 件のコメント
京都のS
2024年7月30日
失礼しました。『枕草紙』ではなく『枕草子』でした。古典ファンの皆様にお詫びいたします。
京都のS
2024年7月26日
掲載ありがとうございました。早くも10回目です(笑)。「光る君へ」や『源氏物語』を題材にしたものは以下です。
・「『光る君へ』から皇族女子の生き辛さを思う 1st season」( https://aiko-sama.com/archives/35405 )
・「『光る君へ』から皇族女子の生き辛さを思う 2nd season」( https://aiko-sama.com/archives/37751 )
・「『光る君へ』から皇族女子の生き辛さを思う 3rd season」( https://aiko-sama.com/archives/38829 )
・「『光る君へ』から皇族女子の生き辛さを思う 4th season」( https://aiko-sama.com/archives/40097 )
・「「光る君へ」から皇族女子の生き辛さを思う 5th season」( https://aiko-sama.com/archives/41148 )
・「「光る君へ」から皇族女子の生き辛さを思う 6th season」( https://aiko-sama.com/archives/41253 )
・「『光る君へ』から皇族女子の生き辛さを思う 7th season」( https://aiko-sama.com/archives/41618 )
・「『光る君へ』から皇族女子の生き辛さを思う 8th season」( https://aiko-sama.com/archives/41824 )
・「『光る君へ』から皇族女子の生き辛さを思う 9th season」( https://aiko-sama.com/archives/42000 )
・「男の嫉妬が英雄を冷遇するなら、トップは女子で良くないか?」( https://aiko-sama.com/archives/35425 )
・「男系固執の鬼どもを退治てくれよう」( https://aiko-sama.com/archives/39215 )
・「革命的皇位簒奪への対策を『源氏物語』から学ぶ」( https://aiko-sama.com/archives/36977 )
・「儒教的男尊女卑に利用されてきた血穢概念を葬れ!」( https://aiko-sama.com/archives/37641 )
・「尊皇心0な輩は永遠に呪われろ!」( https://aiko-sama.com/archives/38188 )