
「光る君へ」は彰子の皇子(敦成親王)出産から道長政権の絶頂期に至る段階ですが、その少し前に中宮・彰子(見上愛)は一条帝(塩野瑛久)の気を引くべく、帝の好んだ『新楽府』(白居易著)の講義を指南役の藤式部(吉高由里子)に望み、そこで興味深い会話が交わされました。同作は詩人の白居易が為政者を風刺する内容ですが、人の心の移ろいやすさに講義が進むと、「私も帝に瑕(キズ)を探されるようになるのか?」と不安になる彰子に、夫婦関係でも君臣関係でも相手の嫌な部分(玉に瑕)が見えたとて「瑕は大切な宝」「瑕こそ人をその人たらしめるもの」(=個性)と諭しました。
ここで思い出されるのは、まひろ(吉高)が清少納言(ファッサマ)から渡された『枕草子』を一読した際の感想、「私は皇后(定子)様の陰の部分も見たい」です。これに対して清少納言は「皇后様に陰など無い」「有っても書かない」と返しました。つまり劇中の『枕草子』は、自身の文学的センスを見せ付けながら定子や定子サロンの素晴らしさを喧伝し、藤原伊周(定子の兄で道長の政敵:三浦翔平)を有利にする目的のプロパガンダ書だったわけです。逆に登場人物の陰や瑕を描いて人物造形に深みを与え、そうした陰ゆえの悲劇をカタルシスへ昇華させた『源氏物語』だからこそ、帝も中宮も女房らも公卿らも惹き付けたのでしょう。言ってみれば『源氏物語』は紫式部の「陰影礼賛」です。また本作「光る君へ」は、瑕一つでも見付けたら鬼の首でも取ったように論い、皇族や皇室関係者でも構わず叩きのめす風潮への苦言のようにも感じられました。
さて、敦成誕生から50日目の儀式(お食い初め)では無礼講の祝宴が行われ、酔った公卿らが乱痴気騒ぎを起こす中、藤原公任(町田啓太)が藤式部に「ここに若紫のような美しい姫は居らぬか?」と問うと、「ここには光る君のような殿御は居ないゆえ若紫も居りません」と言い放ちました。容姿端麗で多才だったとされる公任は、自分こそ光る君のモデルだと思っていたでしょうから、これはルッキズム批判の文脈においても大失態です(笑)。このエピソードを面白がった彰子が後に藤式部を「紫式部」へ改名させると私は読んでいます。
文責:京都のS
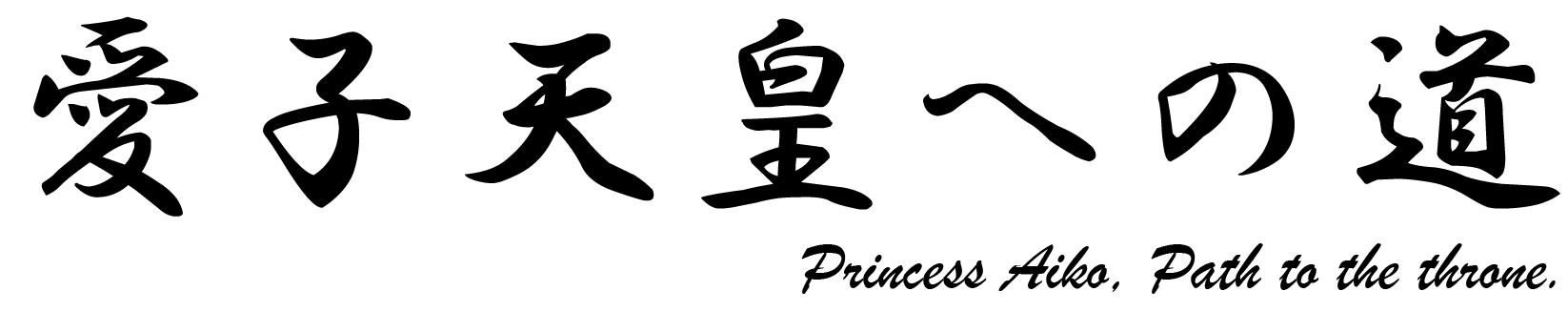

4 件のコメント
京都のS(サタンのSでも飼い慣らすし)
2024年9月25日
SSKA様、※ありがとうございました。翼の左右に拘わらず、「僕の考えた最強の皇室」や「僕の考えた理想の天皇」ほど、押し付けられた対象にも周囲の人間にも迷惑なことはありませんね。
SSKA
2024年9月24日
瑕も陰も無いとは男系固執や万世一系を信じ込むのと同じ考え方で、権力やステータスへの欲望へ通じる所は現在の総裁選を彷彿とさせます。
現実離れした理想を勝手に作られ、期待されて押し付けられる皇室の方々もさぞや迷惑な事だと思います。
京都のS
2024年9月24日
こちらの扉画像は、「光る君へ」で”まひろ”と道長が結ばれる時に銀粉が降ってくるような演出があったことからです。
京都のS
2024年9月24日
ふぇい様、掲載ありがとうございました。早くも16回目です(笑)。「光る君へ」や『源氏物語』を題材にしたものは以下です。
・「『光る君へ』から皇族女子の生き辛さを思う 1st season」( https://aiko-sama.com/archives/35405 )
・「『光る君へ』から皇族女子の生き辛さを思う 2nd season」( https://aiko-sama.com/archives/37751 )
・「『光る君へ』から皇族女子の生き辛さを思う 3rd season」( https://aiko-sama.com/archives/38829 )
・「『光る君へ』から皇族女子の生き辛さを思う 4th season」( https://aiko-sama.com/archives/40097 )
・「「光る君へ」から皇族女子の生き辛さを思う 5th season」( https://aiko-sama.com/archives/41148 )
・「「光る君へ」から皇族女子の生き辛さを思う 6th season」( https://aiko-sama.com/archives/41253 )
・「『光る君へ』から皇族女子の生き辛さを思う 7th season」( https://aiko-sama.com/archives/41618 )
・「『光る君へ』から皇族女子の生き辛さを思う 8th season」( https://aiko-sama.com/archives/41824 )
・「『光る君へ』から皇族女子の生き辛さを思う 9th season」( https://aiko-sama.com/archives/42000 )
・「『光る君へ』から皇族女子の生き辛さを思う 10th season」( https://aiko-sama.com/archives/42094 )
・「『光る君へ』から皇族女子の生き辛さを思う 11th season」( https://aiko-sama.com/archives/42853 )
・「『光る君へ』から皇族女子の生き辛さを思う 12th season」( https://aiko-sama.com/archives/43220 )
・「『光る君へ』から皇族女子の生き辛さを思う 13th season」( https://aiko-sama.com/archives/43538 )
・「『光る君へ』から皇族女子の生き辛さを思う 14th season」( https://aiko-sama.com/archives/44244 )
・「『光る君へ』から皇族女子の生き辛さを思う 15th season」( https://aiko-sama.com/archives/44386 )
・「男の嫉妬が英雄を冷遇するなら、トップは女子で良くないか?」( https://aiko-sama.com/archives/35425 )
・「男系固執の鬼どもを退治てくれよう」( https://aiko-sama.com/archives/39215 )
・「革命的皇位簒奪への対策を『源氏物語』から学ぶ」( https://aiko-sama.com/archives/36977 )
・「儒教的男尊女卑に利用されてきた血穢概念を葬れ!」( https://aiko-sama.com/archives/37641 )
・「尊皇心0な輩は永遠に呪われろ!」( https://aiko-sama.com/archives/38188 )